「卵子老化の真実」「未妊―『産む』と決められない」「出生前診断 ー出産ジャーナリストが見つめた現状と未来」など、多くの著作がある出産ジャーナリスト・河合蘭さん。30年にわたって、日本の出産現場を精力的に取材されています。前編では、出産への興味の原点、出産ジャーナリストの出発点となった「写真を撮ること」や、日本の女性にとっての「産む」歴史について、話を伺いました。
 河合蘭 / Ran Kawai 1986年より出産、不妊治療、新生児医療を追い続けてきた出産専門のフリージャーナリスト。3人の子どもを育てつつ、女性の立場から、現代人が親になるときのさまざまな問題について書いてきた。独身時代に写真家として活動していたことを生かし、2015年からは命を迎える家族や医療現場の写真撮影も行っている。著書は『卵子老化の真実』(文春新書)、『未妊-「産む」と決められない』(NHK出版)、『助産師と産むー病院でも、助産院でも、自宅でも』(岩波ブックレット)、『安全なお産、安心なお産-「つながり」で築く、壊れない医療』(岩波書店)等。『出生前診断-出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』(朝日新書)で、2016年科学ジャーナリスト賞を受賞。講演、放送出演多数。国立大学法人東京医科歯科大学、日本赤十字社助産師学校の非常勤講師。NPO法人日本助産評価機構評価委員。
河合蘭 / Ran Kawai 1986年より出産、不妊治療、新生児医療を追い続けてきた出産専門のフリージャーナリスト。3人の子どもを育てつつ、女性の立場から、現代人が親になるときのさまざまな問題について書いてきた。独身時代に写真家として活動していたことを生かし、2015年からは命を迎える家族や医療現場の写真撮影も行っている。著書は『卵子老化の真実』(文春新書)、『未妊-「産む」と決められない』(NHK出版)、『助産師と産むー病院でも、助産院でも、自宅でも』(岩波ブックレット)、『安全なお産、安心なお産-「つながり」で築く、壊れない医療』(岩波書店)等。『出生前診断-出産ジャーナリストが見つめた現状と未来』(朝日新書)で、2016年科学ジャーナリスト賞を受賞。講演、放送出演多数。国立大学法人東京医科歯科大学、日本赤十字社助産師学校の非常勤講師。NPO法人日本助産評価機構評価委員。
「出産ジャーナリスト」の原点
ー 河合さんは出産や不妊関連の著書も多く、出産ジャーナリストとして様々なところでご活躍されています。「出産」に焦点を当てて自らの仕事にしようと思ったのは、どのようなきっかけがあったんでしょうか。
振り返ってみると、子どもの頃から始まっていた話なんですよね。「生き物少女」だったんです、私。
すぐそばに住んでいたおじが山奥で育った野生的な人で、私もよく山に連れて行ってもらっては、植物やいろいろな生き物を捕まえてきていました。
たくさん飼っては、放して、また捕まえに行って。飼えるものはなんでも飼うっていうポリシーで(笑)、とにかく生き物に囲まれていましたね。
ー ムツゴロウさんか、河合さんか、という自然王国ですね(笑)。
そうそう、でもね、途中から犬・ネコのアレルギーが出てしまって。それまでは獣医さんになることが夢でした。近所の獣医さんにも出入りして、保護された犬の散歩などしていたんです。
ネコを飼ったとき、私にはネコアレルギーがあったのと、放して飼ったほうがおもしろそうだと思って放し飼いにしていたら妊娠して帰ってきました。
一生懸命私が場所を整えて「ここで産むと気持ちがいいよー」と声をかけても、全然見向きもしない。「自分はここで産みたい!」という主張をはっきり感じたんです。
それで子ネコたちが生まれた後、かわいいから縁側でみんな並べて写真を撮ろうと思ってこちらに子ネコを連れてきても、母ネコが自分のところへ連れ戻していく。
そういう、母の本能。
ついこないだまで赤ちゃんだったはずのその母ネコが女性になり、母になって、たくましくなっていく。そうした「出産」を通じた生き物の変化を、とてもおもしろく感じました。
出産に興味を持つきっかけは、他にもたくさん思い当たります。
二十歳くらいで父を看取ったのですが、この時もいろいろ考えたんですね。子育てをしている素敵な女性との出会いもあったし。でも、もっと根っこのところを考えていくと、母への反発もあります。
ー どんなお母様だったんですか?
上昇志向の強い、研究者でした。母の母、私の祖母もまた上昇志向の強い人で。高名な日本画家のお弟子さんになることが決まった途端に結婚させられて、やりたいことを諦めざるを得なかった。
それで、自分が仕事や夢を断念したからか、生まれた女の子4人には「女性も自立せよ」と教育し、中でも勉強が好きな私の母には「あなたはキュリー夫人のようになりなさい」と猛勉強させたんですね。
私の母もその志を受け継いで厚生省の技官になり、将来子どもは持たない、研究に邁進して出世するんだ、それでお母さんを喜ばせるんだ、という道を選んできたんです。
なので、私が生まれたのも本当に偶然というか。
結婚後、引っ越した家が丘の上で、日当たりがとても良くて、なぜか急に「ここに赤ちゃんを寝かせてみたいな」なんて思っちゃったみたいなんです。それで、つい産んでしまったのが、私(笑)。
だけど、産んだら産んだで、もう大変で。保育園もないし、ベビーシッターを雇ったり自分の妹に頼んだりして、四苦八苦しながら私を育てているのを、子どもながらに「大変そうだなあ」と思いながら見ていました。
大人になったら働くのは当たり前だと母を見ながら思っていましたが、「どうしたらこんな苦労せず子どもを育てられるんだろうか」とか、「産むことを背負っている女の人ってどういう存在なんだろう」ということは、自然と考えるようになっていましたね。
ー 当時の時代背景や研究者という世界を考えると、女性で子どもを育てながら働くということは、とてつもなく大変だったでしょうね…。
働くということは、男になるということと同義でしたからね。でも私は、それにすごく反発心を抱いていました。男性社会の中で負けまいと母はがんばっていたけれど、それってなんか変だよね、女性のままで生きられた方がラクだよね、って。
その後私は3人の子どもを出産し、育てながら仕事を続けてきましたが、やっぱり男性のように生きる、働くっていうのはなんかおかしいと思う気持ちは変わらなくて。私が女性として仕事をして母親業も楽しみたいというスタンスでいたのは、母を見て育った影響が大きいと思っています。
撮ること、書くこと
ー 河合さんといえば、ご著書が多いことから「書く」イメージが強いですが、元々は写真を「撮る」ところから出発されているんですよね。写真を始めたきっかけについて教えてください。
小学校の頃、オリンパスペンというカメラが出ました。それを父が、クリスマスプレゼントに買ってくれて。それで友達や家族を撮り出したらおもしろくなっちゃって。
ある日、鎌倉に行った遠足にそのカメラを持って行って、大仏の写真を撮ったら後日それがクラスですごく売れて。自分が写っている写真を買うのはわかりますが、大仏の写真が売れるなんてびっくりで(笑)。そこで「私、もしかしたら写真がうまいのかもしれない」と思ったのがきっかけですね(笑)。
それで、中高と写真部に入りいろいろなものを撮って、大学在学中から、フリーカメラマンとして雑誌の仕事が忙しくなりました。音楽写真、人物取材を依頼されて撮る仕事が多かったのですが、妊娠してからは機材が重いのが不安で「産休」にして。そしてその出産経験から出産に興味が向かい、文章も書きたいと思うようになったのです。

「産みたい人」が何に困っているのか、向き合う
ー 河合さんは話題作も多く執筆されています。出産関係の中でも、「不妊」について書いてみようと思われたきっかけはなにかあるのでしょうか?
最初は出版社の方から声をかけてもらったんです。この仕事しませんか?と。
私も出産ジャーナリストと名乗っているからには、自分こそやるべきだと思いました。日本の「産みたい人」が何に困っているのか、しっかり向き合わなければいけないと。
あとは、不妊治療はなんといっても命の始まりを扱う医療ですから。元・生き物少女としての興味も、純粋にありました。
例えば体外受精が始まるまでは、精子が卵子の中に入っていくところなんて、誰も見たことなかったんですよ。アニメーションなどでは、精子が競争して、1等賞の精子がゴールイン!・・・という感じに描かれたりもするけど、実際はそうではないんですよね。
卵子に到達できる精子はけっこう大勢いて、みんなで卵子を一緒に取り囲むのです。頭部にある酵素で少しずつ卵子の壁を溶かしながら、しばらくうごめいているんですよ。
医師の方たちが言うには、「最初に勢いよく来たやつはたいてい疲れて脱落する」って。私たちの社会でも、よく、そういうことありますよね(笑)。周りで遊んでいたのが、「あ。席が空いた!」って前の精子ががんばっていたところにシュッと入っていって、受精する。
それが生命の現実なんですよね。
ー 不妊の領域と妊娠・出産の領域はすごく近いはずが、なんとなく分断されているところがあって、両方の領域にまたいで活動したり発信されたりしている方はそれほど多くない印象があります。
言われてみると、そうかもしれませんね。
私は不妊治療をしていた人、している人に話を伺うことも多いのですが、不妊治療を経験したという事実を重く考えている方がたくさんいらっしゃることを実感しています。
特に、長く不妊治療をしてきた人は、その傾向が顕著かもしれません。妊娠しても、出産しても、「不妊治療でできた子どもだから…」と背負いすぎているお母さんたちも。
でも、考えてみて、と。
人間の祖先であるとも言われる魚は今も体外で受精して子どもを産んでいるわけだし、どんな生き物だって、ありとあらゆる手段を使って、子孫を残そうとしているわけですよ。そうやって生き物はみんな生き残ってきたわけで、人間だけが特別なわけじゃない。
ー 自然にこだわるといえば、不妊治療だけでなく、たとえば「子どもは母乳で育てなければ」「帝王切開や無痛分娩ではなく、自然分娩で産むべき」などの声も聞こえてきます。
そういう方向に行きすぎてしまうと、どんどん「産むこと」がしんどくなってしまいますよね。
私、母乳育児は大事だと考えているんです。病気の予防になるし、やっぱり粉ミルクを毎回作るより楽なんですね。でも、それは、粉ミルクをあげてはいけないという意味ではない。その人なりに、少しでもあげることが大事なのです。
お産ってすごく幸せなことなのに、「こうでなければ」という思いでがんじがらめになってしまってその幸せを感じられないとしたら、それはもったいないことなんじゃないかって。「普通」とか「自然」とか、そういうものは国や時代が変わればどんどん変わりますから、あまりあてにならないような気がします。
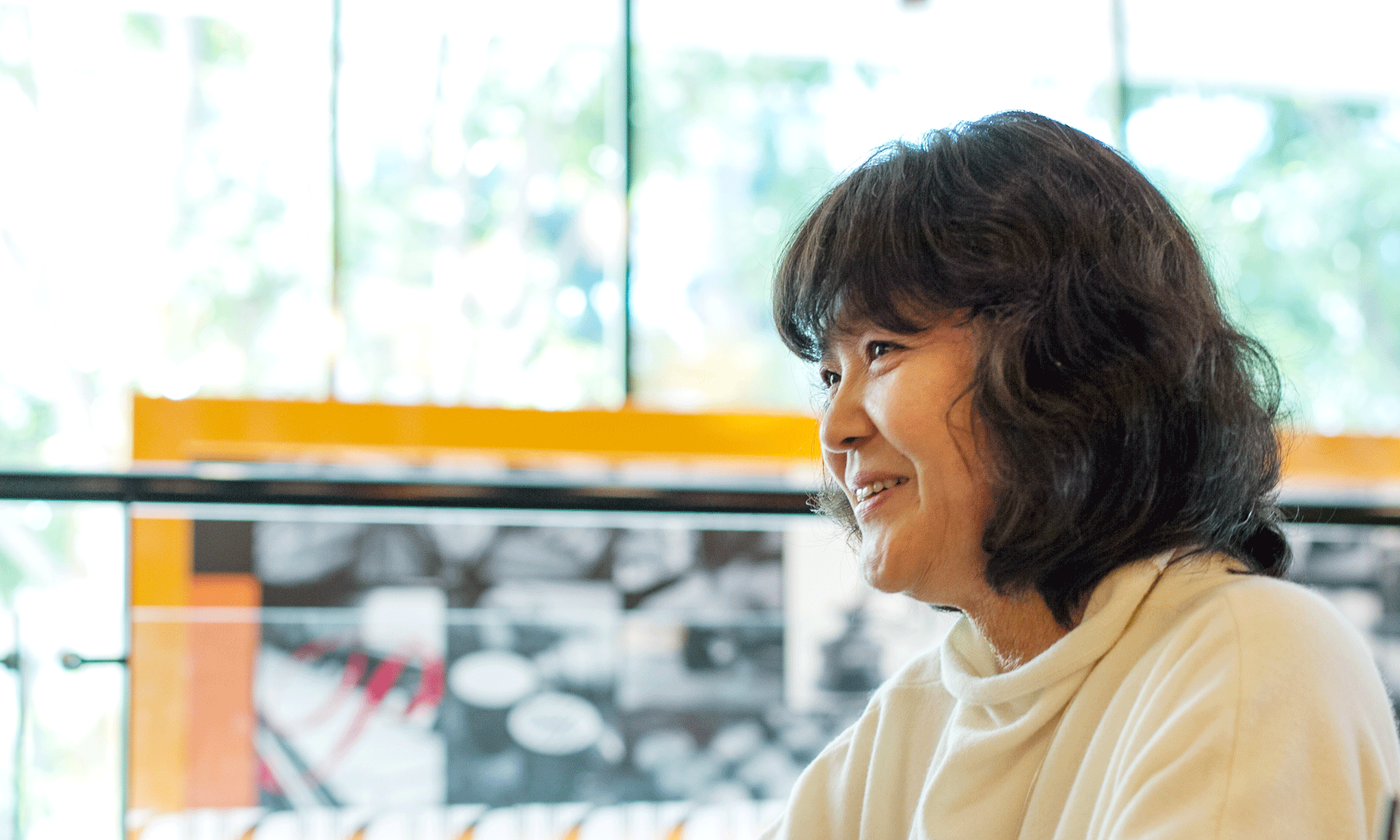
日本の女性にとって「産むこと」とは
ー 以前河合さんの講演で、「歴史的に、日本の女性たちは自分の意思で産む・産まないという選択をしてこなかった。その名残が今でもある」とおっしゃっていたのを聞いて、驚いたと同時に、いろいろなことが腑に落ちた気がしました。
日本は今でも、出産のことを持ち出すと、タブーに触れる感覚がありますよね。
その歴史は、明治時代から始まった「産めよ、増やせよ」の政策が関係していると思っています。第二次世界大戦のときは、政府から出された広報誌に「結婚十訓」というものが掲載されて、そこでは本当に「産めよ、増やせよ」と書かれている。富国強兵政策のピークですね。
ところが、戦争が終わったら、大陸から引き上げてきた人たちなどで一気に国民の人数が増えて、食糧危機が起きる、人口爆発も現実的になって、国が困る。そうなると、今度は「中絶」が必要だということになります。
それで、当時の優生保護法(*注1)、今の母体保護法に、経済的理由でも中絶できるというひとことが書き加えられるわけです。事実上、これが中絶の自由化ですね。この後、空前の中絶ブームが起きます。
— 国の都合によって、女性は産むことが奨励されたり、逆に産まなかったりしてきたんですね。
そう。女性たちが自分で、産む・産まないを決めてきていないんです。国が決めてきた。
ただ、どの国でも大体そういう傾向はあるんです。「この歳になったらこうする」ということを社会が決めてきたという側面ですね。
その傾向を覆したのが、フェミニズムやウーマンリブの流れです。ヨーロッパやアメリカで、女性が「生き方を選びたい」「私のことは私が決める」と起こしたムーブメントです。その中で、リプロダクティブヘルス(ライツ)(*注2)という概念も国際会議で採択されて、欧米ではすごく盛り上がった。
でも日本では、その言葉や概念を知っている人すら、ほとんどいなかった。
日本人が手にした自由がどこかいつも中途半端なのは、こういうところに原因があるんじゃないかと思います。本質的な変革のプロセスを飛ばしてきてしまっているということですね。
もちろん日本でも、興味がある人はそれをすごく考えて実践もしようとするけれど、一方でずっと変わらない人たちがいる。特に権力を持っている人たちは変わらないので、未だに議会でも「おまえが早く結婚しろよ」なんていうヤジが出てきてしまう。
少子化対策の議論でつい軍国主義的な発言をしてしまう人もいますよね。現代の出産支援とかつての出産奨励の違いが、よくわからないのでしょうね。
本当は、そうした発言をおもしろおかしく取り上げて叩くのではなく、本質的な議論をしなければいけないんじゃないかっていつも思います。
(*注1)優生保護法: 1948年から1996年まで存在した、優生学的断種手術、中絶、避妊を合法化した法律。1996年に優生学や断種に関する条項が削除され、現在、母体保護法になっている。
(*注2)リプロダクティブヘルス(ライツ):性と生殖に関する健康・権利と訳される。人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子どもを持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める自由をもつことを意味する。そのための情報を持つことも含まれる。
大切なのは、「自己決定権」に関する本質的な議論
ー 国の都合とはいえ、当時日本で中絶ができるようになったということは、女性の選択としてとても大きな一歩だったんでしょうか。
そう思いますね。中絶って子どもを産むかどうかを決める、とても怖いことでもありますけど、考えてみると、女性の最大の権利なんですよね。命を決められるのですから。
ただ、世界各地で女性が求めたのは単に「中絶する自由」ということだけじゃなくて、「生殖の自由」、つまり、避妊も含めて、何歳で何人産むかを女性が自由に考えたいということだったと思います。
当時それは、まさに、女性が自分の生き方を決めるということでした。自然のままだと、ものすごくたくさんの子どもが生まれてくるのですから。
でも、日本で戦前からあった避妊の運動は、富国強兵時代には非難され、戦後は国策と一致したために実を結びました。実は結びましたが、自己決定権についての議論ができたかというと、そこは疑問です。
その後、団塊の女性たちの中から中絶の自由を守る運動が現れましたが、その運動はおもしろおかしく報道されていたので、そこでも本質的な議論はできないままでした。
ー 子どもの「数」のコントロールだけでなく、障害や病気を理由に、強制的に堕胎や不妊手術を受けさせられる人がいたりなど、衝撃的な歴史もありますよね。
今の「出生前診断」にもつながる話ですね。
国が軍国主義の下でおこなった妊娠・出産への介入は「数」だけではなく「どんな子が生まれるか」もコントロールしようとしたのです。
日本は、病気や障害を持つ人は産んだ子どももそうなると考え、戦後にできた優生保護法の元で、不妊手術を強制できるようにして子どものいる家庭を築く夢を奪いました。
国は国民の遺伝的素質を改善し,強くて優れた集団をつくるべきだという「優生思想」は、かつては欧米各地にあったのです。でも、それは倫理的にも、また科学的にも間違っていたし、ナチズムへの反省もあって他の国では第二次世界大戦以降は大きな過ちと考えられるようになりました。
そういう時期に、日本は、戦前からあった生まれる子どもの「質の管理」を合法的に続けようとしたんです。
それに対し反対運動が燃え上がり、今もそれは続いています。そういうこともあって、今も、日本の政府は妊娠出産に関してはもうこりごり、だんまりを決めようという態度になってしまっている面があるようです。
法律は改正され、今は、強制的な不妊手術などはできません。ただ改正は、国際的な非難を受けそうになったのでさっと行われた、とてもあっけない改正だったようですね。
本当はきちんと反省されるべきことが、あいまいなままになっているのです。 出生前診断に今も国が関わらず学会にまかせっぱなしなのも、そうした歴史的な過ちが尾を引いているのではないかと思っています。
ー 今、「産む・産まない」について国の関わり方は、とてもむずかしいと感じます。「産めよ、増やせよ」の押し付けと思われてもいけないし、でも、少子化一直線の日本の現状では、どうにか子どもを増やしたいという本心もあって。
近年政府は、「少子化社会対策大綱」(*注3)というものを出しています。そこには、「将来のライフデザインを希望どおり描けるようにするためには、その前提となる知識・情報を適切な時期に知ることが重要である」として、少子化解消に向けて、特に学校教育での取り組みを充実させると書かれています。
ここでも本当は「産むのが遅くなると大変だよ」という話をしたいと思うんです。でもはっきりとそうは言えないから、「ライフデザイン」という言葉が使われています。
私は、加齢による不妊の話は、病気予防と同じ「健康教育」だと思うのですが、日本ではそういう風にとらえる人は少ないですね。本当に問題があるのは情報を提供することではなく、自己決定権が確立していないことなのですが。
(*注3)参考:「少子化社会対策大綱」

取材・文 / 瀬名波 雅子、写真 / 内田 英恵、協力 / 真崎 睦美

