「胎児医療」とは、生まれる前の胎児に対して行う医療のことです。日本ではまだ馴染みのない分野ですが、他の先進国では、病院に胎児科があるのが一般的になっています。胎児科とは何か、海外で胎児医療はどう考えられ、受け入れられているのか、日本でまだ浸透していない背景とは…。英ロンドンの病院で胎児医療研修をしながら、NPO法人「親子の未来を支える会」代表でもある林伸彦さん(産婦人科医)に、お話を伺いました。
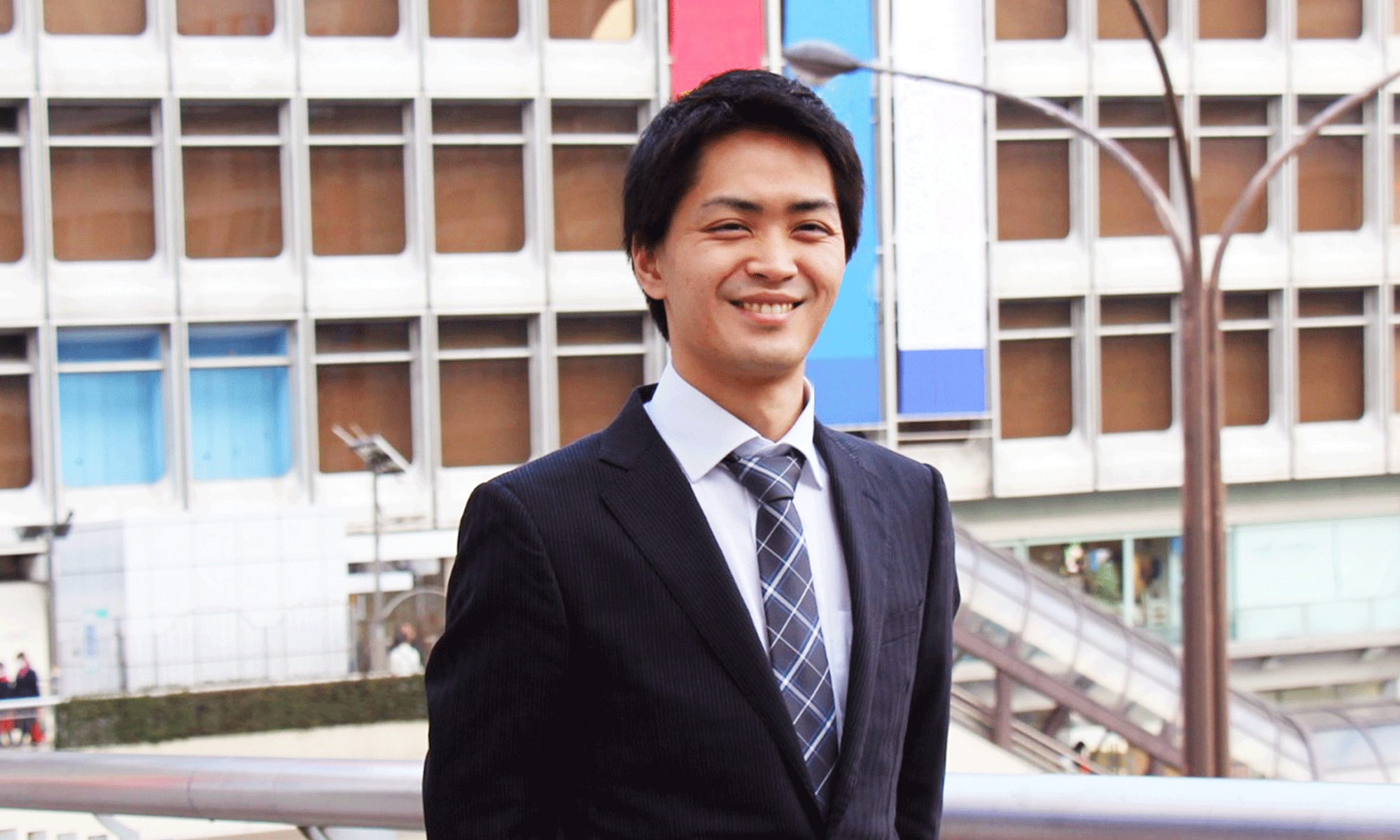
林 伸彦 / Nobuhiko Hayashi 東京大学で分子生物学を学んだのち、千葉大学で医学を学ぶ。出生前診断が普及すると障がいを持つ子が生まれなくなり、より暮らしにくい社会になってしまうかもしれない、という懸念を抱く。同時に、出生前診断を避けると、治療によって防げるはずの障がいや救える命を見逃してしまうというジレンマに課題意識を持つ。出生前診断の意義、胎児医療の倫理観、社会への働きかけ、障がいへの関わりについて、多面的かつ組織的に働きかける必要があると考え、「NPO法人親子の未来を支える会」を設立。
胎児医療との出会い。「この国では、誰がお腹の中の赤ちゃんを診ているの?」
— 胎児医療に関心を持たれたきっかけについて、教えていただけますか。
医学部に入ってちょうど産婦人科研修をしていた時に、アメリカから来た医学生と一緒だったんです。その時、彼に「この国では、誰がお腹の中の赤ちゃんを診ているの?」と質問されました。僕は当然のように「産婦人科が診ているよ」と答えたら、「産婦人科は赤ちゃんのこと全然診てないじゃないか」と言われました。
訊けば、「アメリカには胎児科という専門の科があって、赤ちゃんに病気があればそこで治療する」と。その話を聞いて驚くと同時に、すごく理に適っていると感心したことがきっかけです。
アメリカでは1980年代から本格的な胎児医療が始まっていて、当時すでに30年くらいの歴史がありました。すぐにアメリカの病院へ見学に行くことにしました。
そこで見た胎児医療とは、赤ちゃんを子宮から取り出して手術をし、再び母体の子宮に戻して妊娠を継続させるというような治療でした。当時私は知らなかったのでとても驚いたのですが、「妊娠中なにも手を施さなければ、お腹の赤ちゃんは亡くなってしまう。もしくは生まれてきても障がいを持って生きていくことになる。今治療した方が赤ちゃんにとって良いのに、なんで生まれるまでは経過観察なの?」と言われました。
海外では、生まれる前の赤ちゃんを患者として扱い治療することが広く一般的になっています。その経験ストーリーなども、病院を中心に一般に発信され、病気や治療の社会的理解・啓蒙に繋げています(*注1)。
(*注1)参考外部リンク(英語):フィラデルフィア小児病院(胎児診断&治療科)
胎児科を専門にするため、産婦人科の道に
その後、学術振興会から助成金を獲得し、アメリカ・イギリスなど5か国の胎児科での研修を経て、胎児科を専攻すると決めました。しかし日本には、胎児科という専門医制度もなければ研修システムも、胎児科がある大学病院もありません。
欧米では、赤ちゃんを診ているのは産婦人科、生まれた赤ちゃんを手術しているのは小児外科です。例えばアメリカでは小児外科医が、ヨーロッパでは産婦人科医が、それぞれサブスペシャリティ(*注2)として胎児を診ています。なので海外でも医学部卒業からいきなり胎児科を専門にするコースはないようです。
アメリカで小児外科が行なっているのは、例えば、赤ちゃんを子宮から一度取り出して手術をする、という治療です。ヨーロッパではより低侵襲(*注3)の、例えば腹腔鏡手術のように小さな穴で子宮の中にいる赤ちゃんを治療しようという治療が主流なので、産婦人科が主体となっています。
今後、より母体に負担にならない治療が開発されると考えたため、ヨーロッパのような低侵襲な手法が主流になるのではないかと思い、まずは産婦人科を専門とし、それから海外でも医師免許を取得し、胎児科医として経験を積むと決意しました。
(*注2)サブスペシャリティ:内科・外科・産婦人科・小児科などの基本領域からさらに専門分化した領域のこと。(新生児科・小児心臓血管外科など)
(*注3)低侵襲(ていしんしゅう):従来の開腹手術に代わって、内視鏡(子宮鏡)やカテーテルなどを使い、手術・検査などに伴う痛みや発熱、出血などをできるだけ少なくする医療。

人生は、生まれる前から始まっている。「Fetus as a patient(胎児を患者としてみる)」
― 「胎児医療」について、もう少し詳しくお伺いできますか。
胎児医療、日本ではまだ聞き慣れない言葉ですよね。
そもそも医療は「予防・検診・精査・治療・緩和」5つに分けることができるのですが、その一連の医療を、生まれる前の胎児や胎盤に対して行うことを「胎児医療」と呼んでいます。
例えば葉酸の摂取や風疹ワクチン接種、禁酒、禁煙などは胎児医療で言うところの「予防」にあたります。例として、生まれつきの病気に「二分脊椎」というものがあります。生まれつき脊髄損傷があり、歩行障害や排尿障害、発達障害などが、起きうる病気です。
この病気は、母親が妊娠前から葉酸を摂取することで大抵の場合、予防ができるんです。
そのため、アメリカなど世界約60カ国では日常の食事で必要な量が摂取できるように、食品に葉酸を添加することが義務づけられています。イギリスでは、妊婦は葉酸サプリを無料で受け取ることができます。
日本でも厚生労働省などから葉酸の摂取が勧められてはいるものの、摂取するかどうかは妊婦さんの自己判断に任されています。現状としては、啓蒙はされているものの妊娠前からの摂取には至っておらず、二分脊椎を持って生まれてくる赤ちゃんは増えている状況で、改善の余地があります。
「治療」は特に聞き馴染みがないと思います。そもそも胎児が病気になるという概念があまりないかもしれません。しかしよく考えれば、妊娠中の10ヶ月というのは、人生の中で最も大きな変化を遂げる時期です。
生まれつきの病気というと、もともと病気だから仕方ないと思うかもしれませんが、妊娠中の赤ちゃんの成長がよく理解されるようになり、一部の病気は「もともと病気」なのではなく「人生最初の10ヶ月に発症して進行する」と考えられるようになってきました。生まれてからは早期診断・早期治療が当たり前なのに、生まれる前は診断自体がタブーという現状は、医学的にはナンセンスです。
残念なことですが、妊娠中に流産や死産を経験することは珍しいことではありません。妊娠中に亡くなる赤ちゃんや、生後すぐに亡くなる赤ちゃんもたくさんいます。なんらかの理由で、人工妊娠中絶を選択した方も、その後長く精神的・身体的に辛い時期を過ごすことになります。そのような時に、赤ちゃん自身の痛みを取り除くケアや、幼い命を失った家族へのケアなども、とても大事な胎児医療の中の「緩和医療」と言えます。
「胎児治療」という選択肢
― 「胎児治療」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
胎児期に治療するのには、難しい点もたくさんあります。
赤ちゃんを手術するためには、現時点では母体も手術することになります。健康な母体を傷つけることの倫理観は常に考えなければなりません。それを考慮しても、誕生を待たずに胎児の時に治療を行うことが望ましいとされる病気があります。
例えば、脳神経系の疾患や心臓病、肺の疾患、重症貧血などは、生まれてからでは治癒・再生に限界があるため、生まれる前に治療することでその後の生活の質が大きく向上するとされ、胎児治療が盛んに行われています。
日本で行われている胎児治療
実は日本でも、たくさんの胎児医療が日々行われています。
広い意味では、赤ちゃんがより元気に生まれてこられるようにするというのが胎児医療の考えです。早産を予防すること、妊婦さんの栄養状態を改善すること、妊娠高血圧腎症や妊娠糖尿病を早期に発見して治療をすること、それら普段の産婦人科で行われていることも、赤ちゃんの健康を守る大事な胎児医療です。
しかし、まだお腹の中にいる赤ちゃんが保険証を持つこともありませんし、赤ちゃん自身を手術して助けるというような胎児治療も日本ではまだ浸透していません。
日本で可能な胎児治療に関しては、日本胎児治療グループのHPにまとまっています。
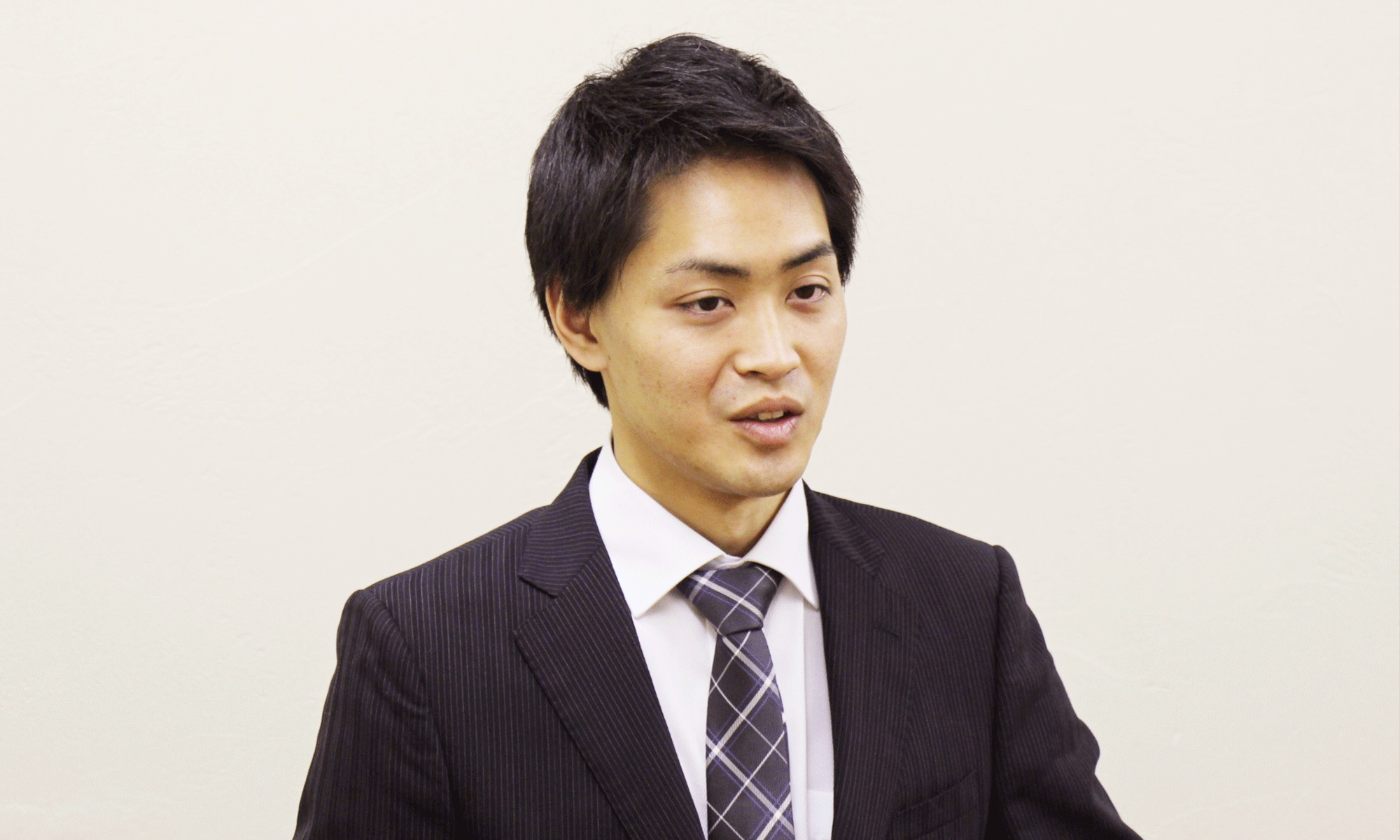
「治療ができる時期に、病気が見つからない」
― 海外と比べて、医療技術は日本も劣っているようには思えないのですが、日本では胎児治療がなぜ浸透していないのでしょうか。
実は私も初めは、「治療」が浸透していないことにばかり着目していたんです。そして「日本で胎児治療をできる人がいないなら、自分が海外で修練を積んで帰って来ればできる!」と意気込んでいました。
しかしその後の出会いの中で、胎児治療を海外で研修して帰ってきた医師たちがたくさんいることを知りました。
ではなぜ胎児医療がもっと普及しないのか。そこにあったジレンマは、「治療はできるけれど、治療ができる時期に病気が見つからない」ということでした。
つまり、例えば妊娠20週で治療すべき病気があった時、日本では妊娠20週ではその病気は見つからない、ということです。
妊婦健診は、「母体の健康」を診るためのもの
― 治療できる時期に病気が見つからないというのは、見つからないのでしょうか?それとも見つけていないのでしょうか?
誤解を恐れずに言えば、見つけていません。
現時点では、日本の医療システムは胎児の病気をスクリーニングする仕組みにはなっていないんです。
親として病気や障がいのない子が欲しいと願うのは自然な感情かもしれませんが、日本の法的な背景・社会的価値観の中では、赤ちゃんの病気を見つけることはしっかり議論されてから行われるべきことです。今はまだその議論の最中であり、社会全体でどう支えていくかを模索しているというのが現状です。
これは単に「日本の医療・社会が遅れている」ということではなく、長い歴史のなかで、病気や障がいがあるからと言って差別されるべきではないという想いがあるためです。この考えは批判されることではなく、むしろ守るべき大切な考えだと思っています。
そうはいっても病気を見つけないことで、防げるはずだった障がいや、守れるはずだった小さな命を放っておくことは、大きな問題だと考えています。
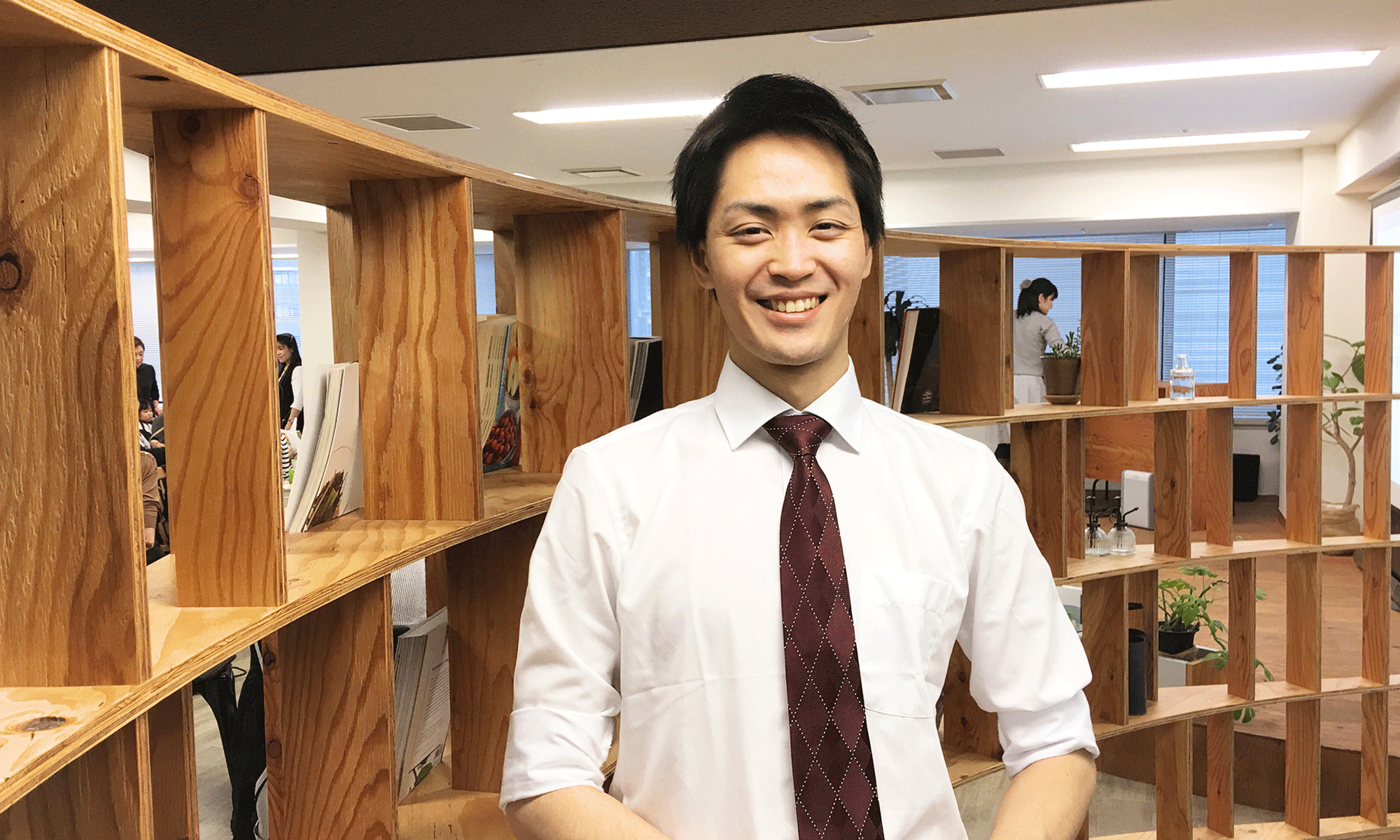
取材・文・写真 / UMU編集部
欧米では当たり前のように行われている「胎児医療」。胎児に対して治療できる病気が増えると聞くと、一筋の「光」のようにも感じますが、一方で、病気を見つけるために出生前診断をすることが、中絶にもつながりうるという「影」も併せ持ちます。
<後編>では、胎児医療をめぐる日本の課題や背景、林さんの思い、NPOの活動内容、そして私たちが今考えるべきことを伺っていきます。

