日本で特別養子縁組をされた親御さんの多くは、実は不妊治療経験者。しかし現実に、「産みたい」と願う当事者にとって、その先の「育てたい」を後押しする養子縁組は、なかなかつながりにくいものかもしれません。昨年出版された『産まなくても、育てられます 不妊治療を超えて、特別養子縁組へ』(講談社)著者の後藤絵里さんは、朝日新聞の記者。なぜこのテーマで本を書こうと思ったのが、どんな課題があり、子どもがほしいカップルがどうすれば親になりたいという願いを叶えられるのか、伺いました。

後藤 絵里 / Eri Goto 世界の様々な話題を、掘り下げた取材で伝える「朝日新聞GLOBE」編集部デスク。2011年にGLOBEで『養子という選択』という特集記事を組み、以来、世界および日本の養子縁組や社会的養護の取材を続けている。プライベートでは1児の母。
取材のきっかけ
ー この本をまとめられたきっかけを教えてください。
世界の様々な話題を伝える「朝日新聞GLOBE」で、2011年11月に『養子という選択』という特集を組みました。
もともと、日本の不妊治療の動向が気になっていて、世界の生殖医療の現状の取材を通して日本の状況を考えてみようと、当時の編集長に相談しました。
そうしたら、生殖医療の話題は色々なところで目にするので、取り上げることの少ない「養子」というテーマに目を向けてみたらとアドバイスをもらいました。
30代半ば頃から周りで不妊や養子縁組の話がポツポツではじめて、私自身、結婚が遅かったこともあり、このテーマは「わがこと」としてカチッと自分にはまったんですね。
アメリカ人の友人に「私は子どもは産めないかもしれない」と話したら、とても自然に「じゃあ養子を迎えればいいじゃない」と言う。一方、日本では、養子を迎えたいと思い、自治体に相談に行った友人が、担当の職員から「養子縁組里親は子どものための制度で、子どもがほしいという理由だけで望むものではない」と言われて、ショックを受けて帰ってきたという話を聞きました。
この差はなんだろう、と思っていたところで、このテーマにめぐり合ったのです。
「養子縁組」特集への反響
ハイライトは、アメリカの養子縁組事情の取材でした。アメリカの人たちは養子縁組を子どもにとって必要な、素晴らしい制度だととらえていて、「なんで養子縁組なんて当たり前のことを取材しに来るの?」という感じでした。どの家庭も子どもとのアタッチメント(愛着)がしっかりできていて、屈託のない子どもたちの育ちを見て、それまで自分の中にもあった固定観念が音を立てて崩れていきました。
GLOBEの「養子縁組」特集には大きな反響がありました。読者からたくさんのメールやはがきをもらいました。年齢は30代から60代までと幅広く、圧倒的に女性からの意見が多かったです。自分が結婚した時にこの制度があったらよかったのにとか、どうして日本は多様な家族のあり方を認めてくれないのだろうとか、いろいろな意見が寄せられました。
この経験を経て、その後の特別養子縁組や里親といった社会的養護の取材へとつながっていきました。
年間の発行回数が限られるGLOBEでは同じテーマで何度も特集を組むのは難しいので、その後は朝日新聞系の他の媒体で角度を変えた記事を書いたりして、まさにゲリラ戦のようにこの問題を紹介していきました。
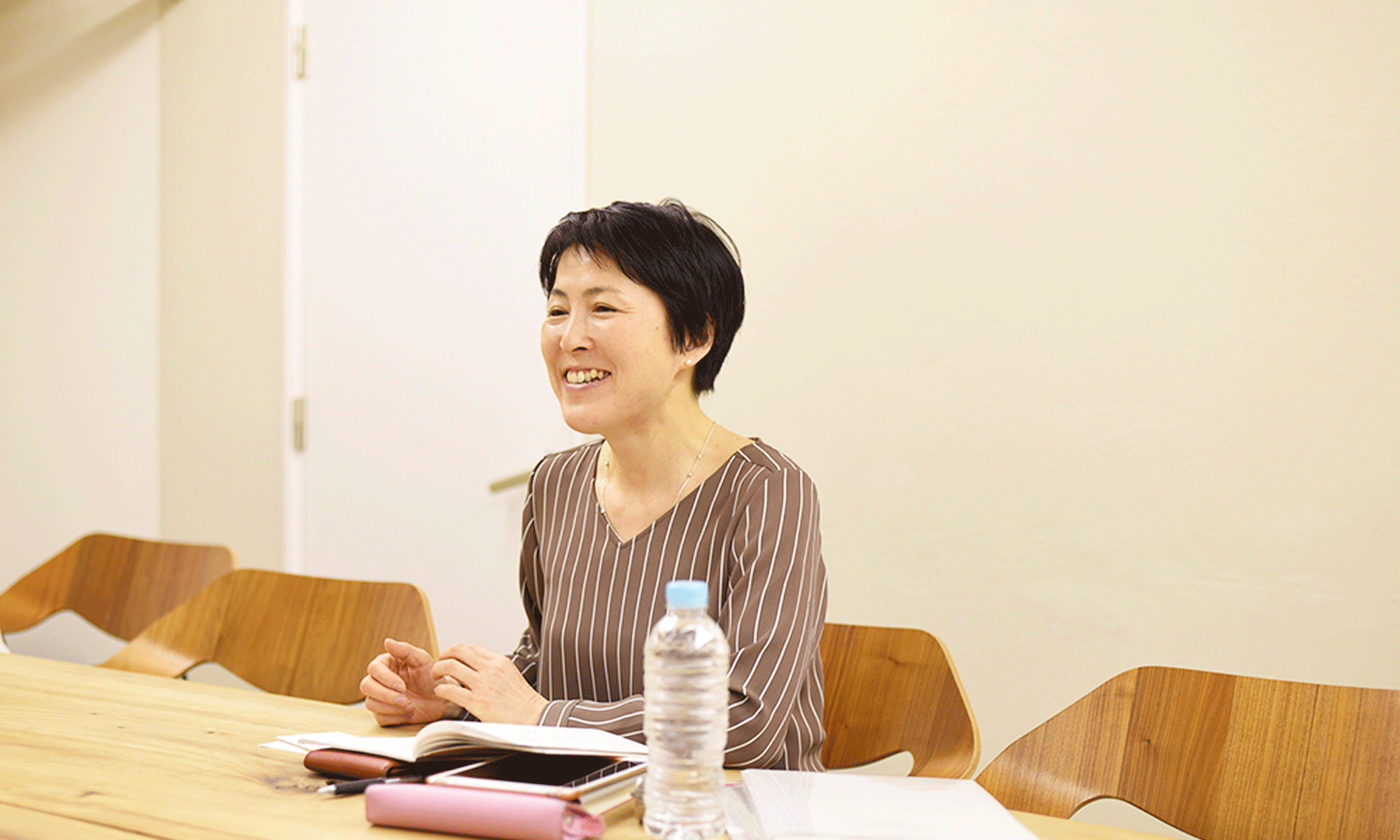
生殖医療と特別養子縁組をつなげるガイドブックを
ー では、最初から本にする目的で取材をしていったわけではないのですね。
そうですね。ただそもそも、「生殖医療はどこまでいくのだろう」という疑問の延長線上でこのテーマに出合ったこともあり、私の中では特別養子縁組と生殖医療の問題とは早い段階でつながっていました。
今でこそ、特別養子縁組が子どものための制度だということは広く認知されていますが、取材を始めた当初は、社会的養護に携わる役所の人でさえも「なんで個人の家庭のことに行政が手を差し伸べなければいけないんだ」という態度でした。
「里親は推進します、でも養子縁組は別です」というスタンスで、特別養子縁組制度の意義が正しく認識されていませんでした。
また、子どものための制度であるから、親になりたい夫婦のエゴでこれを捉えるべきではないと、不妊治療との関連で語ることをタブー視する雰囲気もありました。
― ただ、児童養護施設にいるままが本当に子どものためかというと……。
本当にそうなんです。どこに視点を置くかだと思ったんですよね。
欧米では当たり前のように不妊治療と養子縁組がつながっているのだから、これだけ不妊治療が普及している日本でもそうなれば、特別養子縁組はもっと広がるんじゃないかと。
そのためには、親になる意欲があって、なりたいと願っている人に、こういう選択肢があって、そんなに恐ろしいものじゃないということを伝えられる「手引書」となる本を書きたいと思うようになりました。
― サブタイトルにも「不妊治療を超えて、特別養子縁組へ」とある通り、不妊で悩む「子どもがほしい」人たち向けに、特別養子縁組のプロセスや養親さんの体験談を具体的に紹介されていて、ガイドブックのように分かりやすい本ですね。
はい。やっぱり体験者の話を聞くことで、背中を押されることがあると思うんです。その一歩を踏み出すかどうかで、その後の人生が変わってしまう。なら、背中を押してあげないともったいないと思ったのも大きかったです。

「子どもの権利」という視点
― 日本では、子どもの権利や人権という概念が薄いようにも感じます。
去年の6月に児童福祉法が改正され、「子どもには健やかに育つ権利がある」ということが初めて日本の法律に明記されました。
これは画期的なことです。ただ、どうやってこれに実効性を持たせていくかはこれからの議論です。
法律ができただけで終わってしまうことも十分ありえるからこそ、「子どもには育ちの権利がある」という意識がもう少し広く、多くの人のところに落ちていかないと、今までそうした視点が法律になかったことがおかしいということにも気づかないでしょう。
特別養子縁組を阻む壁
― 本の中で、特別養子縁組と不妊治療との関係について、日本ではこの2つが並列ではなく順列だとおっしゃっています。日本の場合、不妊治療を終えて、諦めてから、ようやく特別養子縁組を考えるけれど、欧米などでは不妊治療も特別養子縁組も同時並行で考える、という。
そもそも欧米では養子縁組という選択肢は広く知られているので、言われなくてもみんなわかっているわけです。不妊治療の期間も比較的短くて(*注)、一定期間、トライして難しかったら、すぐに養子縁組など、別の選択肢に切り替えるとか、治療と並行して養子縁組機関の門も叩いてみるとか。自然な形でパラレルとなっています。
― それが日本の場合、なぜそうならないのか。ひとつには養親さんの事情でしょうか。
養親さんにとってのメンタル面の壁はあると思います。養子縁組自体が、何年か前まではあまり人に言うものではないという空気だった。不妊治療もかつてはそうだったと思います。
養親さんに聞くと、養子縁組を検討していると言ったとたんに友だちが引いたとか、親に反対されたとか。そういう周囲の反応は大きく影響していると思います。
― 養子縁組に踏み切ろうと思っても、人の意識という面のハードルにぶつかるんですね。
あとは、やはり不妊治療の“レール”に乗ってしまうことも大きいと思います。
いつまで続けるのか、他に方法はないのかなどと考え始めても、お医者さんをはじめ、周りから「もう諦めるんですか? まだ42歳だから大丈夫ですよ。頑張りましょう!」みたいにおしりを叩かれて、やめどきを見つけられず、なんとなく続けてしまう。
だけど実はお医者さんもジレンマを感じていて。不妊治療に携わるお医者さんに聞くと、本音では、これ以上治療を続けても妊娠の可能性は限りなくゼロに近いと思っても、医者の立場ではやめろと言えないと。
たぶん、どれだけ難しいかということは、お医者さんが一番分かっているんだと思います。でも、患者さんが「がんばる」と言っている時に、お医者さんがそれに対抗する「敵」みたいになってしまうのが忍びないと……。
だからこそ、二つの世界に橋を架ける仕組みがあれば、色々なことが変わっていくのではないかと思います。
― 医療業界の方では、まだ特別養子縁組を勧める動きまではないのでしょうか。
社会的養護の観点からは、日本産婦人科医会が2011年に、望まぬ妊娠を背景にした赤ちゃんの「虐待0日死」を防ぐ手段として、特別養子縁組という制度があることを現場の産科医たちに知らせるガイドラインを作っています。
問題は法律と同じで、トップがかけ声をかけても、なかなか現場に浸透しないことです。
でも、民間のあっせん団体の方と話していたら、最近は不妊治療クリニックが特別養子縁組に関心を持ち始めていて、事業について問い合わせがあると言っていました。
医療の世界からのアプローチは間違いなく増えてきているし、お医者さんのマインドも変わってきていると感じます。
(*注) 体外受精の「出生時一人あたりの治療周期」2014年実績では、日本は米国の約3倍(日本 8.3周期 : 米国3.0周期)
<参照>Figures from the 2014 Assisted Reproductive Technology National Summary Report by CDC / 平成 27 年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告より

養子のタブー視は高度成長と核家族化の影響
―「血縁」重視という日本的価値観も関係している気がします。夫婦でも考え方は違うし、両親、親戚など、「自分の血を分けていない子をもらってどうする」と反対するとか。
それはもう、親御さん含めて、経験したことがないから躊躇するんですね。他人の子を育てるなんて、苦労を背負い込むだけだからやめた方がいいと。
でも、私が話を聞いた夫婦は例外なく、「実際に子どもを迎えてみたら、親(子どもにとっては祖父母)のほうが孫にべったりになった」と言います。
子どもの存在自体が放つ力があるんです。子どもはそこに存在しているだけで、何もしなくても周りの愛を受けて、大人たちを変えていくんです。なので、周囲の心配はたいていの場合、杞憂という感じですよね。
― 私たちの祖父母、曽祖父母ぐらいの年代の方たちに聞くと、養子縁組は普通だった、よくある話だったと言われます。
そうなんです。世代間の断絶があるんですよね。養子縁組に対する社会の態度の変化は、1970年代以降の高度成長や核家族化が影響しているとも言われます。
戦後しばらくは、日本中が貧しくて、養子としないまでも、実の親が育てられない子の面倒を他人がみるというのは結構あったと。でも、国が豊かになって子どもの数が減っていき、一方で持ち家化、核家族化が進むと、みながそれぞれの家庭にタコツボのように閉じこもり、養子縁組は特異なケースとされて家庭の秘め事みたいになっていったと。
そう考えると、日本に受け容れる土壌が全くない、ということでもないのかなと。
民間のあっせん団体の取り組み
― 民間のあっせん団体は内容も費用もそれぞれで、どう選んでよいか分からない人も多いと思います。本の中でもいくつかの視点がありますが、迎えた養子のルーツや親族の病歴など「知る権利」の面でも、実親のケアやその後の繋がりがあるかないかで違うのではないかと思います。
それは大きいですね。どの団体も、基本的には妊娠相談という意味での実親ケアは重視していると思います。ただ、実親とどんなふうに関係を構築しているかは、団体によってさまざまです。ルーツ探しなどは、子どものその後の人生に関わることですから、「とにかく子どもが手元に来ればよい」ということだけでは絶対にないんです。
インターネットのアプリで縁組のマッチングをおこなう団体もありますが、とても問題があると思います。ただ、どんなにマスコミが批判して、何度、行政の指導が入っても、子どもがほしい親御さんは藁にもすがる思いだから、そうした団体への問い合わせは絶えないのです。
生殖技術の世界で時に起きてしまう「どんな手段でもいいから子どもがほしい。それも健康な赤ちゃんが」というのと同じことが、今後、特別養子縁組の世界でも起きていくと思います。
ほとんどのあっせん団体では養親の年齢制限がありますから、どこにも登録できない人も出てきます。私が知り得た情報では、ネット上で赤ちゃんをあっせんする、ある団体に登録した夫婦の中には70代の夫と50代の妻のカップルもいました。他の団体では年齢もあって養親候補として受け付けてもらえず、その団体に行き着いたのです。
― だからこそ今、手引書としてこの本を出すことで、押さえておかなくてはいけないポイントをしっかり盛り込んだんですね。
そうなんです。特別養子縁組という方法を知ったとしても、実際に何から始めればいいのか、民間団体を選ぶときはどういう点に気をつけたらよいのか、情報が圧倒的に足りないのです。だから、みんな手探りです。
子どもと巡り会いたいと思ってリサーチを始めても、ネット検索でひっかかるのはマドンナやアンジェリーナ・ジョリーといった海外セレブの話だったり、事件になるような極端な養子縁組の事例だったり。しかも怪しい団体に限って、検索で上位にあがることがままあるんです。
ネットの情報はまさに玉石混合なので、信頼できる情報を探す術を持たないと、怪しい団体につながって、結果的にひどい目に遭うことも十分にあり得ます。「子どもがほしい」という人たちの切実な思いを利用しようとする事業者は、今後も出てくるでしょう。
あっせん法のこれから
― 欧米のように養子縁組が進んでいる国では、あっせん団体の質はどうなっているのでしょうか。
アメリカの場合は、基本的に自己責任の世界です。ただアメリカでは養子縁組を仲介する事業者は、州の認可を得なければなりませんから、そこで一定のスクリーニングがされます。
それと、アメリカは養子縁組に関してハーグ条約に批准しており、養子縁組をする際のルールが整備されています。それに基づく「ハーグ認定」という、第三者評価の仕組みもあります。団体や個人間の縁組を仲介する弁護士を選ぶ時に、基準にするモノサシがあるわけです。
日本の場合、いま現在は養子縁組事業は「届け出制」で、団体を客観的に評価する機関もない。少し前までは、民間の団体で迎えてトラブルに遭っても自己責任、という雰囲気でした。
去年、日本で「特別養子縁組あっせん法」ができて、養子縁組事業をする場合は自治体の認可を得なければならなくなります。でも、実際にどんな制度になるかの議論はこれからです。公正・透明な運営をしない団体は、淘汰されていく仕組みをつくらないとならないと思います。
― 選ぶ方も団体の持続可能性を見極めないと、子どもが大きくなって自分のルーツを知りたいと思った時に、その団体がないという事態になりかねない。
そうです。だから選ぶ側も賢い目を持ってほしい。時期によって関わり方に濃淡はあれ、その団体とは一生の付き合いをしていくことになるんですから。今後、「あっせん法」の政省令を整備していくなかで、あっせん団体の認可基準をどうすべきかといった議論が出てくるでしょう。

写真 / 望月小夜加、取材・文 / 矢嶋桃子
産まなくても、育てられます
不妊治療を超えて、特別養子縁組へ(健康ライブラリー)
著者:後藤 絵里
仕様:B6判 並製 総238頁
発売日:2016/11/23
定価:本体1,400円(税別)
ISBN:978-4062203296


