お腹の中の赤ちゃんに対して行う、「胎児医療」。産婦人科医であり「NPO法人 親子の未来を支える会」代表理事でもある林伸彦さんに、<前編>では、胎児医療についての概要と、国内の現状を伺いました。続くこの<後編>では、日本が今抱える課題とその背景、今後の展望についてお話を伺います。
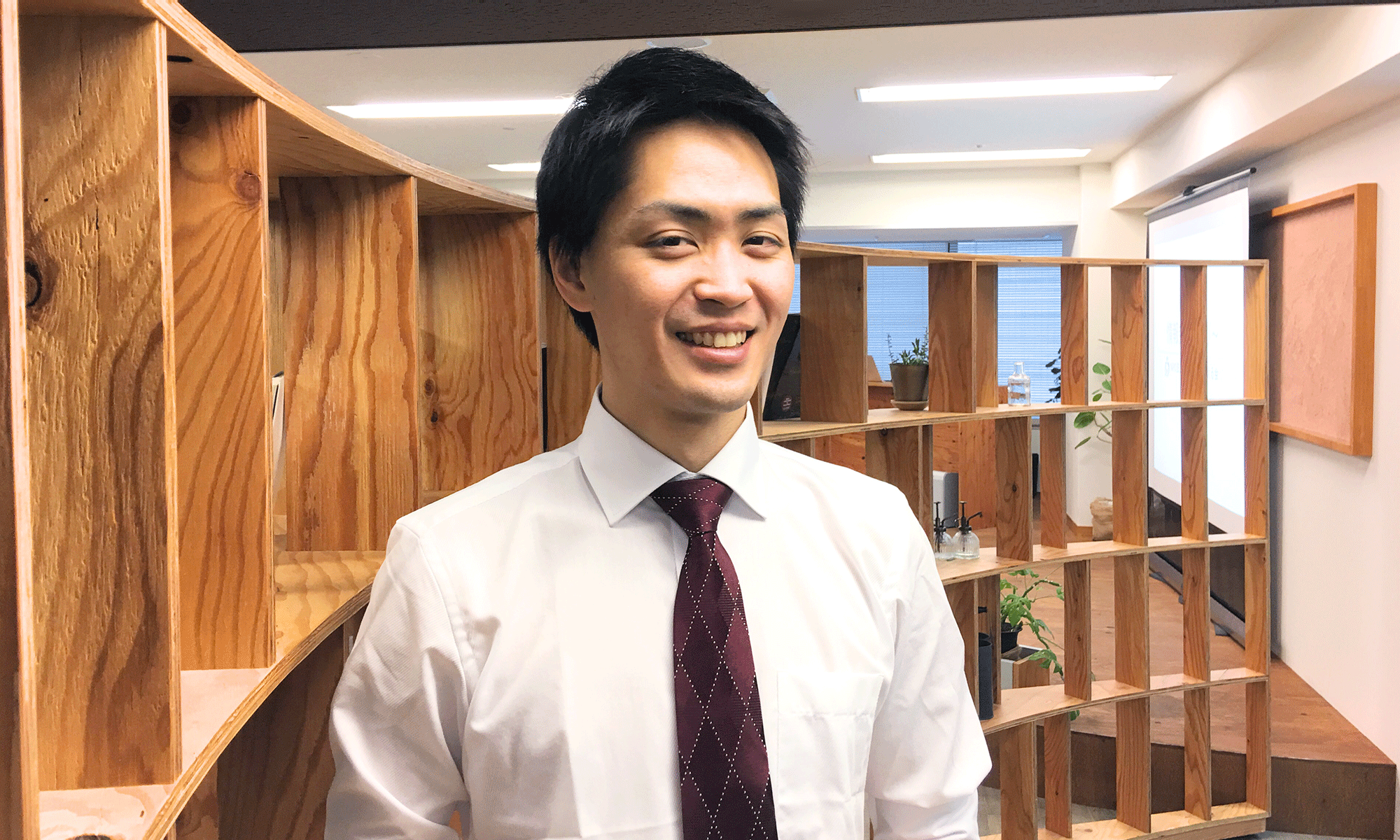
林 伸彦 / Nobuhiko Hayashi 東京大学で分子生物学を学んだのち、千葉大学で医学を学ぶ。出生前診断が普及すると障がいを持つ子が生まれなくなり、より暮らしにくい社会になってしまうかもしれない、という懸念を抱く。同時に、出生前診断を避けると、治療によって防げるはずの障がいや救える命を見逃してしまうというジレンマに課題意識を持つ。出生前診断の意義、胎児医療の倫理観、社会への働きかけ、障がいへの関わりについて、多面的かつ組織的に働きかける必要があると考え、「NPO法人 親子の未来を支える会」を設立。
救えるはずの胎児の病気が診断されない理由
— 胎児の時に治療できる病気もある中で、日本では積極的に見つけていないということでしたが、そこにはどんな要因があるのでしょうか?
医師が胎児の診断そのものをためらってしまうのにはいくつもの要因が絡んでいます。あくまで個人的な意見ですが、大きな課題として私が感じているのは主に3つです。
その1 「母体保護法」の意味。命を救うという医療者の使命
まず、胎児を救おうと思って診断しても、結果的に中絶につながりえるという葛藤があります。
ー 胎児の病気を知ることは両親の権利という考え方もあると思います。特に妊娠初期であれば、中絶という選択肢を選ぶ方もいると思いますがいかがでしょうか。
そもそも日本では、胎児の病気を理由にした中絶は認められていません。
よく「妊娠22週前であれば」、と言う方がいますが、それはあくまで「身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れのある場合。あるいは暴行や脅迫などによって妊娠した場合」の話で、赤ちゃんの病気を理由にした中絶は、どの週数であっても認められていません。「赤ちゃんの病気」を理由に中絶することがあった場合、医師が堕胎罪に問われることになります。
この母体保護法には、病気や障がいがあっても排除されるべきではない、どんな命も平等に生まれてくる権利があるはずだという考えがあります。この考えは、胎児治療や胎児健診が進んでからも、守るべき大切な考えだと思っています。
また、多くの医師は、「命を救う」「治療法を見つける」ということを胸に医師を目指し、医学を学び、医療を行なっています。病気や障がいがあったら救いの手を差し伸べたいという心情があるため、中絶につながりえる検査をためらうという背景もあると思います。
その2 病名が障がいとなっている現状。障がいに向き合えない社会
赤ちゃんの25人に1人は、心臓病などなんらかの形態上の異常があります。代謝異常や発達障害も含めれば、さらに多くの子が、生まれた時点でなにかしらの病気や障がいがあります。出生前診断というと「ダウン症候群」ばかりに焦点が当てられることも多いですが、ダウン症候群は生まれつきの病気(症候群)のうち8分の1程度に過ぎません。
また、ダウン症候群の出生前診断を希望する方には、ダウン症候群がどういった症候群で、どのような生活を送るのか全く知らない方もいます。
この状況を考えると、病気そのものではなく、漠然としたイメージや不安によって、病名が障がいになっていると言えるのではないでしょうか。そのままの状況では、救うために診断を進めても、結果として「よくわからない、不安だ」という理由で失われる命が増えると想定されます。
一方で、胎児治療を行っても、完全に病気を治せないこともあります。
そういった、障がいを軽くするという治療の場合、治療を受けるということは障がいを受け入れることを意味することにもなります。
そのようなとき、産まない選択をする方もでてくることは容易に想像できます。前述の母体保護法のことも重なり、このことも医師が胎児の診断をためらう理由の一つになっていると思います。
その3 胎児治療が普及していない
胎児への診断が進まない3つ目の大きな理由として、胎児治療が進んでいないことが挙げられます。卵が先か鶏が先か、という話と似ていますが、治療が確立していなければ診断する意義が薄れ、診断されることが稀なままであれば治療も確立しません。
治療そのものは違法ではないため、たまたま診断された子だけでも治療をしたらと思うかもしれませんが、広く一般に普及していない医療を、選択肢の一つとして提供することは、想像以上に難しいことです。
治療を受ける立場になって考えてみるとわかりますが、これまでに聞いたこともなかった検査や治療を、リスクを理解した上で自律的に選択して受けることは勇気と行動力がとてもいることです。まだ一般に広く普及していないからこそ、先進医療などとして認められることや、周囲の方々のサポートが必要不可欠だと考えられます。
例えばがんの診断を受けた方に手術と抗がん剤治療の選択肢を示した時には、「難しいことはわからない。他の人はどうしていますか?先生ならどちらを選びますか?」と言われることが多々あります。
たしかに、突然がんの告知をされた時に、医療者の意見を求めるのは当然のことでもあります。一方でリスクや副作用のない医療はなく、また、治療に100%はありません。どの選択肢が一番納得できるものか、最終的に決めることができるのは患者さんなのです。
もちろん選択をいつでも患者さんに丸投げするという意味ではありません。確立されていない医療であったり、複数の選択肢がある時には、患者さんが自律的に選択することが難しく、かつその選択が実質的に患者さんにとって「良い結果」になるとは限りません。そのような時には医師としての経験や想いを踏まえて、一緒に意思決定していくことが必要だと思います。
ただ、どの選択肢を選ぶかの判断が医師に委ねられることが増えると、医師が初めから限られた答え(選択肢)を用意してしまうことにつながる可能性があります。そのことが、「たくさんの選択肢から患者さんが選んだ治療法を、できるだけ安全に提供する」という立場から医師を遠ざけてしまいかねないのです。
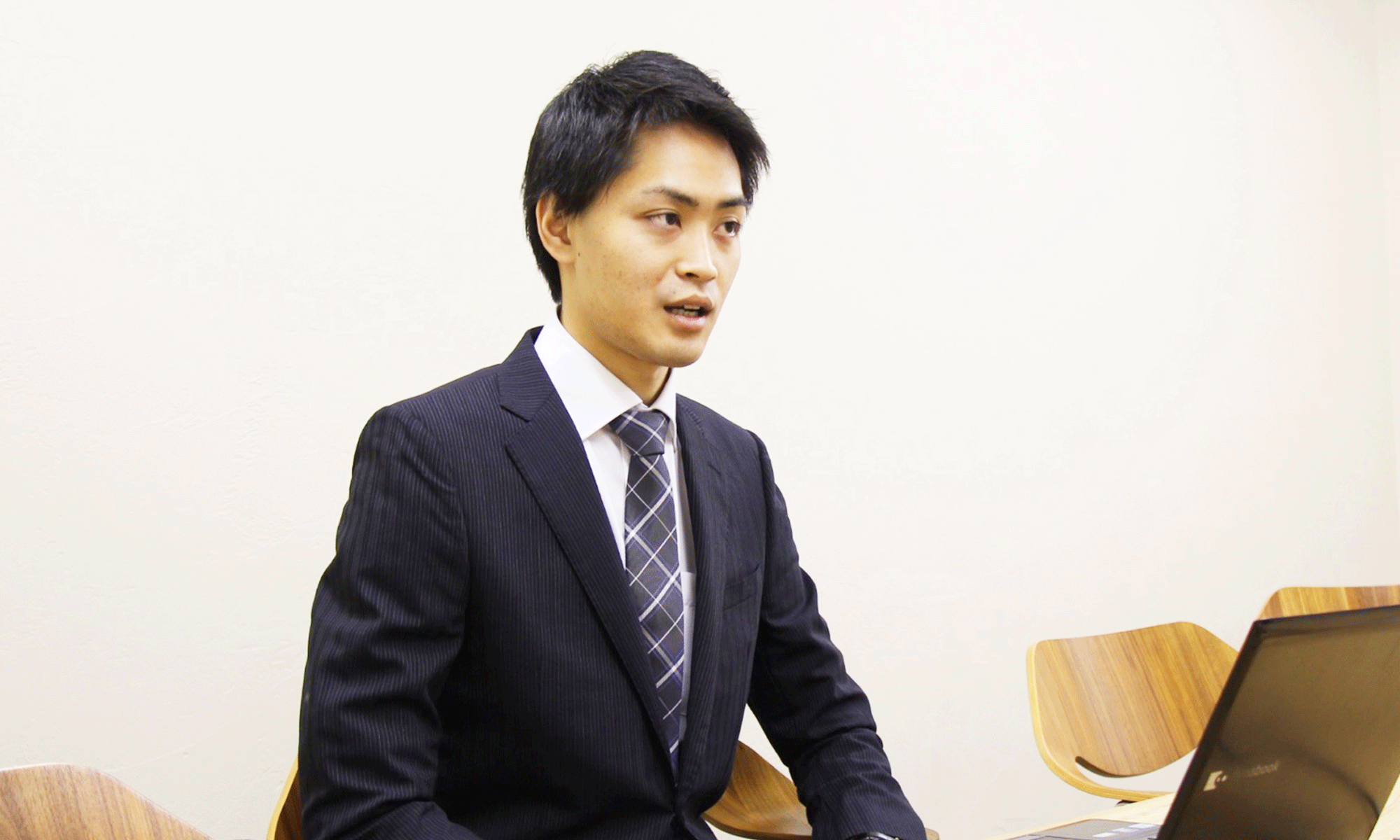
選択肢を知った上で、「家族が決める」イギリス
— その状況は、例えば研修先のイギリスではどう考えられているのでしょうか?
まず前提として、「医療に“絶対”はない」こと、「決めるのは患者である自分たち」であるという考えが、患者さんや社会に浸透していると感じています。日本では、新しい治療法や薬剤は、海外で十分に安全性や有効性が確認されてから普及する流れをとることがほとんどなので、聞いたことのないような新しい治療を、自分自身でリスクを理解して受け入れるということに慣れていないのかもしれません。
イギリスで診療をしていて、胎児に病気があるとわかった時は、「それはどんな病気か」「その病気を持って生まれたらどういう生活が送れるのか」と聞かれます。そのあとに、「妊娠中にできることがあるのか、ないのか」という議論になります。
生まれてからの治療しか選択肢がない場合はそう説明しますし、生まれる前にできる治療がある場合は、そのメリットとリスクを説明します。
治療をした場合としなかった場合の予後の差や流産率などたくさん質問されるので、医師は多くのデータを頭に入れておかなければいけません。しかし、家族と議論する中で、納得できる選択を自律的に決めてもらうことができます。
治療の結果、流産という結果になってしまうこともありますし、障がいを持って生まれてくることもあります。しかし、家族は自分たちの選択に納得をし、現状を受け入れているように思います。そして何よりも社会が、その家族の選択を批判することなく支持してくれます。
出生前診断は本来、生まれてくる赤ちゃんとその家族が納得する医療を受けるためのもの
― 日本でも、出生前診断(*注1)を受ける夫婦は年々増加していると言われています。
そうですね。特に、ダウン症候群などの染色体異常の有無を調べる新型出生前検査(*注2)が話題になっています。前述した通り、生まれつきの病気(症候群)は様々あり、「出生前診断=染色体異常の検査」ではありません。しかし日本では、染色体異常の出生前検査を「する」か「しない」かで議論が止まっているように思います。
本来は、検査というのは医療の入り口の一つに過ぎません。例えば手のレントゲンで脳腫瘍がわからないのと同じように、染色体検査では心臓病や脊椎の病気などはわかりません。
検査にはそれぞれ目的があり、なにか一つの検査で全てがわかることはありません。
どんな生まれつきの病気を心配して、どんな目的でどの検査を受けるか、そして検査した上で、治療や緩和などの選択肢を納得して選ぶための環境が整っているか、そのような議論が必要です。
新型出生前検査の登場をきっかけに、出生前検査について議論がなされるようになる中で、毎年数え切れないほどの、救えるはずの命が救えていないという現状に、不甲斐なさを感じます。
そして、本来は「病気や障がいがあっても差別されるべきではない」という考えで存在する母体保護法が、結果的に出生前に病気を診断することをためらわせ「病気や障がいとともに生きる子どもたちから、胎児治療という選択肢を奪っている」ということを皮肉な状況とさえ感じてしまいます。
(*注1)胎児に先天性の病気、奇形、染色体異常がないかどうかを調べる検査の総称
(*注2)母体血を利用して、21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー、13トリソミーの3つの染色体の数の異常を調べる検査。母体年齢が若いなどの条件下では、誤って陽性になる確率が高いことから、検査前のカウンセリングや結果の解釈に注意が必要。
記録に残らない、「産めない本当の理由」
先ほどもお話した通り、日本では「胎児の病気」を理由にした中絶は違法なので、中絶が行われる際には、ほとんどの場合「経済的理由」として中絶が行われます。
その現状自体は徐々に社会に知られるようになってきました。過去の判例などからも、胎児の病気を理由に妊娠を中断することは暗に認められていると考える人もいます。
しかし、このことの問題は根深く、「実質的には中絶という選択肢を提供できるようになってきたとしても、それが社会的法的にサポートされておらず、中絶を選んだ家族は、周囲にも言えず孤独に身体的精神的苦痛を感じている」という問題が残っています。
さらには、記録上は経済的理由となっているため、実態の把握が困難になっています。胎児の病気が分かったとき、「なぜ家族が産まないという選択をせざるをえなかったのか」、それを把握して社会を改善して行かない限り、本当の意味で、誰もが安心して妊娠子育てできる社会、病気や障がいを隔離しない社会は作れないと考えています。
この入り組んだ課題に向き合うために設立したのが「NPO法人 親子の未来を支える会」です。

「選択」の前に、受けられるサポートを知ってほしい
― 具体的にはどのような事業を展開されているのですか?
私たちが行なっている事業の柱は、インターネットを通じて行う「ピアサポート」(同じような立場の人によるサポート)です。
病名や障がいをキーワードに検索し、複数の仲間に相談をすることができます。居住地などで絞り込むこともできるようになります。インターネット上なのでいつでも気軽に情報を検索できますし、匿名で参加できることも大事にしています。
― インターネット上でのピアサポートはなぜ必要なのでしょうか?
妊娠中に赤ちゃんの病気が見つかった時、「妊娠を続けるかどうか」という選択を数日以内に迫られることが多々あります。
医療者は、検査の方法やリスク、病気や障がいの原因・予後・治療法を説明することはできます。しかし、どんな子育てになるのか、子どもの教育はどうなるのか、どんなサポートが受けられ、将来は結婚・妊娠ができるのか―。そういった具体的な情報提供は、体験を持つ患者家族の方が適していると考えています。
インターネット上でのやりとりがベストな方法とは考えていませんが、個人情報管理の厳しい医療の中では、同じような境遇の方同士をつなげるというのは難しいのが現状です。
特に、稀な障がいが見つかった場合は、患者家族が同じような経験をされた当事者の声を聞く機会はほとんどありません。また、遺伝科のない地域の方や、対面での相談をためらっている方などの救いにもなると考えています。
その一方で、仲間に相談することで不安がすべて解消するとは考えていません。
それでも、漠然とした不安を具体的な不安にすることで、将来の見通しが立ち、「本当は生み育てたかったけど、情報不足で産む決心ができなかった」という人は少なくなると考えています。 また産んだ後で、「こんなはずじゃなかった」と悩み苦しむ方も救えればと思っています。

「命の選択のための出生前診断」から「マイナス一歳児への医療としての診断」へ
その他、既に障がいや病気にかかわる子どもたちへの就学支援や、兄弟支援、両親のメンタルケアなども行なっています。胎児のうちから支援を受けられるためのプラットフォーム作り、病気や障がいを持つ子を生み育てる際のお金の相談(ライフプランニング)なども行い、出産前に色々な準備をできる環境づくりをしています。
そして日本では受けられない胎児治療を海外で受けるためのサポートなども行っており、「出生前診断は命の選択のためのもの」という誤った認識を、少しずつ変えられたらと考えています。
― 海外で治療というと大きなことに感じますが、問題などはないのでしょうか。
法的には全く問題ありません。ただ、海外で胎児治療を受けることは、治療という選択肢を提供する上で一時的な課題解決になる一方で、やはり難しいことがたくさんあります。
まずは、金銭面の課題です。自国で提供できていない治療を海外で受ける際に、国から治療費をサポートしてもらえるような仕組みを持つ国もありますが、日本にはそのような制度はありません。現状は、家族の自己負担にて渡航して頂いています。臓器移植ほど高額ではありませんが、それでも数十万円から数千万円の自己負担になります。
社会保障に関する不安も課題です。日本で認められていない治療を海外で受けてから生まれた子どもに対して、社会保障がきちんと行われるのか、任意保険にちゃんと加入できるのか。ご家族はそういった不安も抱えながら、海外渡航を決意しています。
人生の中で「知る機会」が多くあるイギリス
― 例えば、出生前診断後に提供される情報としては、日本とイギリスではどのような差があるのでしょうか?
出生前診断後に家族へ伝える情報はそれほど差がないと思います。
違いがあるとすれば、診断前に個人が持っている経験や情報だと考えています。つまり、病気や障がいがある方と、これまでの人生の中でどれだけ関わってきたか。また、自分自身が持つ「障がい」を意識し、いかに社会に支えられて暮らしているか、という認識に違いがあると感じています。
日本は、教育課程でいえば、普通学級と特別支援学級、支援学校に分かれていることが多いので、例えばダウン症と言っても、身近な人を思い浮かべることがなかなか難しいのではないかと思います。
イギリスではみんなインクルーシブに教育を受けるようになってきているので、妊娠して胎児にダウン症や、こんな障がいがある、と分かった際に「ああ、じゃああの子みたいな感じかな」と想像がつきやすい。だから「漠然とした不安」というのは少ないように思います。
胎児医療を取り入れた他の先進国
― 新しい医療がスタートするとき、どのように社会に受け入れられていくのでしょうか?
赤ちゃんを一度子宮から出して胎児手術をし始めたアメリカをはじめ、諸外国では子宮鏡、腹腔鏡手術、遺伝子治療を行なっているのですが、よく考えてみるとそれぞれ始めた時点では「はじめての手術」だったわけです。
歴史がない、完璧ではない医療だけれど、様々な安全試験・臨床研究を経てヒトに適用できるとなった時に、それを実践した。一番肝心なのは「本人が納得しているかどうか」が大事な社会なので、できたことだと思うんです。
もちろん、海外で行われているものだから問題ない、ということではないですし、本人が良ければいいというものではありません。だからこそ、日本での胎児医療の普及も、焦らず社会の変化とともに行うべきだと感じています。
日本では、何かあった時に起こるであろう批判を考えると、医療者も新しいことには挑戦しにくいところがあります。たとえ治療を受ける本人はリスクを承知の上で治療を受けたとしても、実際にそのリスクが現実となったら、社会問題になり得る。
治療がうまくいったとしても、「生まれる前の命に介入するなんて」「障がいを防ぐ・生まれつきの病気を治療するという発想が優生思想だ」などと批判を受けるかもしれません。
そういう社会の価値観・倫理観を守りつつどのように進めていけば良いか、今まさに議論が必要で、ひとりひとりの声を発信することが求めれていると思います。
日本のこれから
― 日本で胎児医療を進めていくために、必要なことはなんでしょうか?
まずは、「どのようにしたら、病気や障がいを排除することなく、救える命を救い、そして誰もが安心して妊娠し子育てができる社会を作れるのか」、それを考える必要があります。障がいや病気を持って暮らしている方たちへの理解の促進と支援、そしてこれから生まれてくる子どもたちへの社会的サポートなどを、同時進行でやらなければならないと感じています。
また、胎児医療を日本でも広く取り入れると世論が動いたとしても、胎児の診断・治療ができる医師を育成するということが課題となります。現在日本でも、胎児治療を行なっている施設や病院はあります。しかし、広く一般に胎児健診を行うとなったとしたら、胎児の病気を診断・治療できる医師は不足することになります。さらに、胎児の病気を見つけた時に、きちんと小児科や家族会、行政などと連携できる環境を整える必要もあります。
— 課題はたくさんあるようですが、私たち個人レベルで今日からできることはありますか?
赤ちゃんの病気がこんなにも多いということや、生まれる前から治療できる病気があるということを聞いたことがあるという人が増えることが、物事を変える大きな力になるように思います。そういう意味で是非この記事を拡散してもらえると嬉しいです。
また、胎児医療や出生前診断に限ったことではありませんが、「本人たちが 悩んで決めたことなんだから応援しよう」と周りが言えたら、自ずと個々人にとってベストな選択ができるようになるのではないかな、と思っています。
誰もが、自分たちが持っている選択肢を必要なときに知ることができて、選んだ時にその決断がサポートされる社会をつくりたい。それは、妊娠・出産に限らず、仕事や生き方においても言えることです。
そのために私たちにできることを模索していきたいと思います。

取材・文・写真 / UMU編集部

