「女性は結婚し出産するもの」。日本社会に今もはびこる社会通念が、自分の人生を生きたいと願う女性たちを苦しめることは少なくありません。
不妊治療技術の進展は、子どもを望む多くの女性の救いとなっていますが、未婚であることや産まない・不妊治療をしないという選択も、同様に尊重される社会であってほしいものです。
32歳で不妊症が分かった石橋麻希さんは、以来、社会が求める女性像と、自分が望む生き方とのギャップに葛藤を抱き悩んできました。それから10年。今に至るまでの気持ちの変遷を見つめ直し、率直に語っていただいた、貴重なインタビューです。

石橋 麻希/Maki Ishibashi 静岡県出身。看護師免許取得後、順天堂大学医学部附属静岡病院の救命救急センターにて看護師に従事、ハードな勤務によるストレスで半年以上生理が止まってしまう状態を経験。その後アメリカ留学を経て2008年から聖マリアンナ医科大学病院のハートセンター、画像放射線治療センターにて看護師の経験を積む。不整脈、子宮内膜症などの持病を抱えながら勤務を続けていたが、2017年大学病院を退職。現在は聖マリアンナ医科大学の医療AIやテクノロジーの研究に研究技術員・看護師として所属している。
虚弱で医療機関が身近だった幼少期から、看護師を志すまで
のびのび育ちつつ、「礼儀正しさ」も教え込まれていた子ども時代
―まずは、まきさんの小さいころに遡って取材を始めていきたいと思います。どのようなご家族のもと、どんな幼少期を過ごしましたか?
もともとは両親と兄の4人家族ですが、小学校高学年になってから、母方の祖父母と同居するようになり、6人家族になりました。大正生まれで戦前戦後を経験した祖母は、家父長制度の真っただ中で育ち、昔ながらの価値観を大事にする人。
一緒に暮らし始めてからは、「女の子なんだから家の手伝いや家事をするように」、「兄は男だから家事をやらなくていい」、「父より先に食事をしてはいけない」と言われることがとても多くなりました。
とはいえ、我が家は父が工場を自営していましたので、帰ってくるのが夜8時や9時。そこまで晩御飯を子どもは待てないですから、母が「いいんじゃない。先に食べましょう」って言ってくれて。祖母との間に母がいつも入ってくれていたので、そこまで祖母の影響は受け過ぎずにすんだと思います。
両親はどちらかというとのびのび私を育ててくれましたね。習い事もいろいろさせてもらって。あまり自分に自信のない子でしたが、性格は明るかったです。
ただ、父の工場の従業員さんには、ちゃんと挨拶する、お菓子をもらったら御礼をする、大人の会話に割り込まないなどと注意されることもあり、私も怒られないように大人の前ではいい子でいようとすることが多かったと思います。
―きちんとされた家庭で育ったのですね。医療の世界にはどのように興味を持っていったのでしょう?
もともと子どもの頃から病院のお世話になることが多く、生まれた直後はNICUに入院し、その後も発熱やケガのため救急医療機関を度々受診していました。
11歳で月経が始まり、中学生になると成長期も相まって貧血がひどくなり、そこからは総合病院に通院するようになりました。医師から体育や部活を控えるように言われるほど症状は重く、鉄剤などを飲んで治療していました。
幼少期から、周りの友達と比べると医療機関を受診する回数が多く、医療従事者が身近でしたし、中学生のときにお世話になった看護師さんが、「看護師っていいわよ」と言っていたのも頭の片隅に残っていました。
当時はインターネットも一般的ではなかったですから、世の中にどんな職業があるかよく知らないのが正直なところで、目に見える、周りの大人が就いている職業が仕事のすべてだと思っていたところもありましたね。最終的には、高校の進路指導の際に母と担任の勧めで看護学校を1校だけ受験したところ合格し、そのまま進むことにしました。

大腸がん終末期の女性と出会い、「一人前の看護師」が目標に
―幼いころから病気がちだったことが、看護師を目指すきっかけにもなったのですね。実際に看護の世界に入っていかがでしたか?
実は看護学生になってからも生理痛や不正出血などトラブルが続き、下血のため19歳で大腸カメラも経験しました。自身の体調と向き合いながらということもあり、とにかく勉強についていくのが大変で、当初は落ちこぼれ学生として過ごしていました。
ですが、ある年の臨床実習で、大腸がんの終末期を患うフィリピン人の女性を受け持つことがあり、これが一人前の看護師を目指す原点になりました。
彼女は病気に対する知識が教育として与えられていなかったようで、“どんな病気も治療すれば治るもの”と思っていらっしゃいました。自分が末期がんであることがよく理解できず、「私って死んじゃう病気なの?」って学生の私に何度も聞いてくるのですが、なんて答えていいか分からない。
異国の地で亡くなるということを余儀なくされた彼女を前に、ただベッドサイドに座って、話を聞いて、身体を拭かせてもらうことしかできませんでした。そのときこう思ったんです。もし私が国家資格を持った一人前の看護師だったら、彼女にもっとちゃんと関われたかもしれないと。
彼女とは、亡くなる数日前に再びお会いする機会があったのですが、モルヒネで意識が朦朧とする中でも私のことを覚えていてくれたのが、今も忘れられません。国籍に関係なく、適切な医療を提供できる看護師になりたい。彼女との出会いでそう思うようになりました。
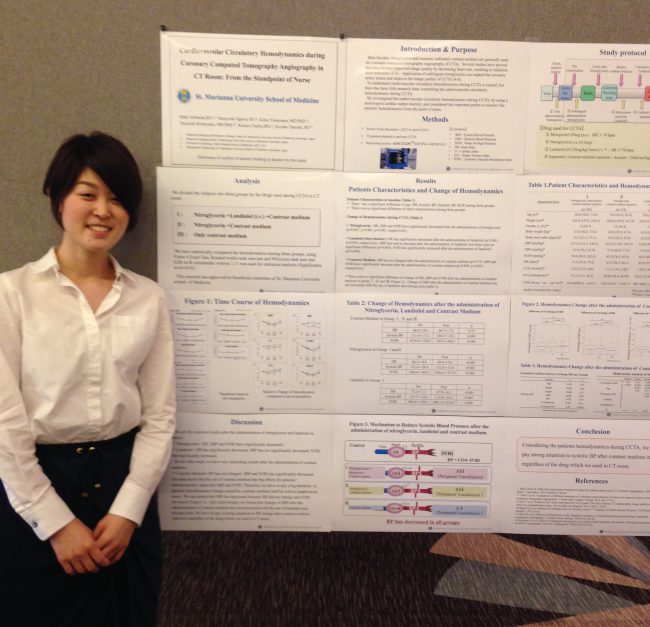
学会の研究発表でハワイへ
社会通念を気にしつつも、本心は違う道を望んでいた?
―看護師になってからは、キャリアと結婚、子どもを産む、産まないなど、まきさんの中で描いていたライフプランはありましたか?
それほど深く考えたことはなかったのですが、自分の両親も含め親世代や周囲が一般的に思うように、「ある程度看護師のキャリアを積んだら結婚、妊娠、子育てをするもの」と表面上、うっすら思っていたようには記憶しています。
ですが、先日母と話していて改めて気づいたのですが、実際の私は、成長過程で結婚や家庭を作ることを前提とするライフプランを強く描いたことはなかったようなんです。というのも、母から「当時からあなたは、英語が話せる看護師になりたいから絶対留学しますって、そればっかり言っていたわよ」と言われまして。
社会の価値観にのっからないといけないという想いをどこかで持ちながらも、じゃあ本心はどうかというと、今思えば、心の奥底には結婚、出産して、子育てを頑張りたいという気持ちはそれほど強くはなかったのでしょう。
もともと子どもが得意でなかったということも、影響を与えているかもしれません。看護実習で小児科を回るときも、何とか小児科の実習を回避したいと思ったほど苦手意識があって。
入院して、痛い治療を受け辛い思いをしている子どもを見るのがとてもいたたまれなかったし、かといって保育園に実習に行ったら行ったで、元気な子に何をしたらいいのかが分からない。子どもが苦手なのに、自分も周囲と同じように将来、出産や子育てをしないといけないのかな、自分にできるのかなと、疑問や不安を持つことはよくありましたね。

32歳で「子宮内膜症・卵巣嚢腫・子宮筋腫」とトリプル診断
生理が半年止まり、看護師長に叱られる
―「子どもが苦手」というのも、なかなか現場で発言しにくい空気があっただろうと想像します。そうした実体験を経て、徐々にご自分の本心に気づいていかれたんですね。ところで話は戻りますが、新人看護師としての日々は大変に多忙だったことと思います。その当時のご体調はいかがでしたか?
実は、看護師になった最初の年、生理が半年以上ストップしてしまいました。配属されたのが大学病院の救命救急センターで激務だったのと、当時はまだ三交代勤務で、20時に日勤が終わって、0時から深夜勤務をしなくてはいけないような状況。
仕事も勉強もこなす中で、ご飯を食べるタイミングを逃すわ、睡眠も不規則になるわで、さまざまな要因が重なったことが原因と考えられました。
特に看護師になって最初の3カ月はストレスも重なり大変でしたから、自分としては「生理が止まるくらいのことはしょうがないかな」と思っていましたね。医療従事者のくせにこう言ってしまってはダメなのですが、仕事中はナプキンを変える暇もないほどですから、生理がこないほうがかえって楽だなとも感じたものです。
でも、半年もその状態が続いた辺りでいよいよまずいと思って、当時の師長さんに相談したら、「あなた、看護師でしょう。何やっているの!」とナースステーションで叱ってくださって。その場で師長さんが婦人科の先生に電話をかけてくれて、すぐに診察を受け、ホルモン剤を打ってもらって、そのまま通院することになりました。
―看護師長が怒ってくれたことで、受診につながったのですね。その後、生理の不調は解消されたのでしょうか?
生理周期自体は回復したのですが、その後もPMSや生理痛に悩まされました。でも仕事は変わらず忙しく、キャリアを積まなくてはという焦りもあって、痛み止めでなんとかコントロールしながらやり過ごしていました。
「子宮内膜症・卵巣嚢腫・子宮筋腫」の確定診断がついたのは、32歳のときでした。たまたま同僚の診療放射線技師にMRIの練習台をお願いされ、受けたら「石橋さん、卵巣が腫れているようだから婦人科にいったほうがいいよ」と言われて。
不調を長年放置してしまったので自分の身体に申し訳なくもあって、改めて受診したところ、卵巣が6㎝ほど腫れていることが分かり、子宮内膜症とそれに伴うチョコレート嚢腫、そして1㎝大の子宮筋腫が見つかりました。
「社会、親、パートナーとなる男性への罪悪感」が一気に押し寄せた
―長い期間を経て、生理の不調の原因がようやく突き止められたのですね。
はい。思えば20代で仕事が大変で生理が止まってしまったとき、大学病院の婦人科とは別に、クリニックの婦人科も受診していたのですが、そこの先生からも、「もしかしたら積極的に子どもを望めないかも」と言われていました。子宮の頸部が赤くなっているなど、様々な不調を踏まえ、そう思われる所見があったそうです。
その後も、卵巣の腫れは指摘されていましたが、手術はなるべく避けたかったですし、生理痛も薬でコントロールできていましたから、そのままにしていました。
そこから年月を経ていざ、不妊の原因ともなる確定診断がついた。その時私に芽生えたのは、パートナーになる男性に対して、結婚してもらうのが申し訳ないといった複雑な感情でした。
社会通念から結婚は「しなくてはいけない」もの。けれど、持病がある私を選んでもらうことはできない。持病が分かっていて不妊治療する可能性が高いので、男性にもそういった経験をさせてしまうのは申し訳ない、そもそも私を選ばせることが心苦しい--。そんな想いが、一気に押し寄せてきたのです。
そして、両親が期待しているであろう結婚、妊娠、出産を私がしないことに対し、自分の家族にも申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
ちょうどそのころ、義姉の出産に付き添う機会があったんです。子どもが生まれることの幸福感を目の当たりにして、私はこんな幸せを家族に与えてあげられないんだなと思うと、罪悪感を抱かずにはいられませんでした。

これまでの自分の頑張りが、全否定されるのではないか
―もともと、本心では「子育てよりも仕事を頑張りたい」という気持ちがあったまきさんですが、いざ不妊症の可能性が高いことが確定的になり、その現実のリアリティに大きなショックを受けてしまったということなのでしょうか。
そうですね。本音は出産、子育てをそこまで望んでいなかったという感情は今でこそ自覚できることで、当時はまだ揺らぎの中にいて、政治家などが「女性にはたくさん産んでもらいたい」とか、「産まない=生産性がない」という発言をするのを耳にしては、自分には女性としての価値がないのだと傷ついていました。
だからこそ、医療従事者として、人の命を救うために全力を尽くさないと許してもらえないと、自分自身をすごく追い込んでいたところがありました。私が看護師の仕事を精一杯頑張るのは、子どもを産むという形での社会貢献ができないぶん、仕事で貢献するしかないと思っていたところもあったんです。
ですから、もし産めない自分を否定されたら、人の命を助けるためにしてきた自分の頑張りさえもすべて否定される、当時はそこまで張り詰めた感情がありました。
ただ同時に、全力で仕事をすればするほど、病状としては悪化してしまい、さらに価値がないのだと自分を責めてしまう悪循環にもなっていました。家族や社会に対して、産めなかったとしても自分は存在していていいんだ、許して欲しいー。翻弄される現実の中で、正直なところそんな気持ちも強かったですね。
子は授かりもの。神の領域に手をつけることへのためらい
―複雑な感情の中にいらしたのですね。かたや、不妊症を自覚した当時のまきさんはまだ30代前半。不妊の可能性が高くても、その後原因疾患を治しつつ、不妊治療をすれば子どもを授かる可能性も十分に残されていました。それについてはどうお考えになっていましたか?
そうですね。主治医の先生からは、不妊症であることは言われましたが、だからといって妊娠を諦めるよう諭されたこともありませんでした。そういった意味でも、医師としてとてもフラットに接してくれていたと思います。どちらかと言うと当時は、逆に私自身が早々に自分の妊娠、出産を諦め、自分には価値がないんだと決めつけていたように思います。
あと、実は不妊治療については、自分の中でも今も整理しきれていないところもあるんです。確かに内膜症や卵巣嚢腫があっても産める可能性はゼロではなく、生殖チームにお願いして体外受精をすれば授かるかもしれない。
ですが、当時は今ほど不妊治療の技術も進んでいませんでしたし、治療費用も高い。それに人によって受け取り方はそれぞれだと思いますが、わざわざ精子を採取して持ち込んでもらうのが、私にとっては男性のプライドをへし折る行為のようにも思えてしまって。
あくまで私個人の感じ方であり、治療中の方を否定するつもりは全くないのですが、自分が好きになった男性にそれ(精子の採取)をしてもらうのが嫌だなと……。
不妊治療してまで子どもが欲しいのか、という気持ちもその頃からどこかにありました。これは親の影響もあるかもしれません。うちの親は、いい意味で「子どもは授かりものだから」とよく言うんですね。子を授かるかどうかは、神の領域だと。
私自身、医療現場で働いていると、神様の意志でどうにもならない領域があるというのを実感することがあるんですね。特に救命救急の現場にいると、どんなに医療が発達しても、どのタイミングで人が亡くなるか、助かるか、まったく予想がつかないことがある。
そういうのを目の当たりにすると、命を授かるということにも、人の手が介入しきれない部分があるのではないかと個人的には思ってしまうのです。
もちろん、実際には不妊治療で多くの方がお子さんを授かり、幸せになっていますから、素晴らしい技術であることには間違いありません。でも、自分自身が不妊治療をしてまで子どもが欲しいかと言われると、ちょっと分からない。どうしてもこの人の子どもを産みたいと思える相手が現れたら、考えが変わることもあるのかもしれないのですが……。

「産んでも産んでいなくても、自分は自分」
40歳をきっかけに、泣きながら母に謝罪
―不妊症の可能性が高いと診断を受け、葛藤を経験された当時から10年が経ちましたが、この間、お気持ちに変化は?
実は40歳と、一昨年の42歳になったときと一度ずつ、母親に泣きながら謝罪をしたことがあるんです。
女性として、母のように結婚、妊娠、出産をしていないこと。そういった人生を歩まないことで、家族に心配をかけているかもしれないこと。孫の顔を見せるという、娘として望まれているであろう役割が果たせていないこと。こうしたことへの罪悪感がとても強いことを、母にはどうしても伝えたくて。
―お母さまの反応は?
「そんなこと考えていたの?まあ、そんな気もしてたけどー」って。拍子抜けするものでした(笑)。
「そんなに思い悩んでいたんだとしたら、お母さんがそんなふうに育てたってこと?ぜんぜんそんな気持ちないけどねー」って。私に気を遣ってそう言っているというのではなく、心からそう思っているようでした。私とは性格が反対なんです。子どもは授かりものなんだから、しょうがないものはしょうがないじゃんと。
こうやって明るく話す母ですが、私が身体が弱く、子どもができにくいことで相手として選ばれなかったらどうしようと悩んでいたのには、母も薄々気が付いていたようです。
でも、「そんな相手、こっちから切ってやればいいのよ。お母さんならそんな相手はいらないわ」ってキッパリと言ってくれて。嬉しかったですね。
そして、こうも伝えてくれました。私が結婚していないことは家族も特に気にしておらず、妊娠、出産に関しては授かりものといわれるだけあり、どうすることもできないこと。家族はそれに対し責める気持ちは全くないと。そして、私自身が幸せでいてくれることが一番の願いなのだと。
それを聞いて私は、肩の荷が降りたような気持ちになりました。そして、母と話をする中で、実は私自身も「自分の子の顔をみてみたい」という気持ちをどこかでもっていたのだと、そんな思いもよらない感情の存在にも気づくことができました。
40の節目で気持ちを吐き出せたのに、再び42歳のときにも謝罪したのは理由がありました。実はこの頃が、確実に自分の中で「産まないで生きていく」ことを受け入れた時で。今一度、母に自分の生き方について、話をしておこうと思ったんです。
母の反応は、1回目のときとほぼ同じでした(笑)。「まだ言っていたの。あなたはいつも悩むのね」って。先日も電話で話をしたとき、「二回謝ってくれたけど、好き勝手に生きている割には、そこばかりくよくよ悩むのね」って言っていましたね。
―お母さまに話したことで、気持ちの整理がついたのですね。
そうですね。母に話したことも大きかったですし、周りの友達に自分自身について話をしたことも、自分を肯定していく後押しになりました。
それまでは抱えてきた葛藤を人に打ち明けたことがなかったのですが、何かのきっかけで、自分が不妊に悩んでいて、それが背景にあって結婚や出産を選択していないというのをその場にいた友人たちに話したとき、受け入れてくれる人が想像以上にたくさんいたんです。
その場には、子どもがいる友達もたくさんいましたが、子どもを産んだからといって、私の感情を理解できなかったり、はねつけたりするような人はいなくて。みんな、そんな私の悩みや葛藤も含めて、私自身のことをまるごと受け止めてくれました。
「産んでいても産んでいなくても、結婚していてもしていなくても、いいじゃん。がんばって患者さんのために仕事をするのが、まきちゃんでしょう」って。たくさんの友人がこう言ってくれて、そんな言葉を聞くうち、私もこれでいいのかもと思えるようになっていきましたね。

臨床現場を離れて(ボランティア活動)
大切なのは、自分の生き方を自分がどう捉えるか
―全てのプロセスを経て今、まきさんは「子どものいない人生」について、どんなことを思いますか?
そうですね。現在は子どもも、そしてパートナーもいませんが、それも私の人生なんだと思えています。私は医療従事者として、赤ちゃんから100歳を超える方までたくさんの方に関わらせてもらっていますが、そうした中で、本当にいろいろな人生があるんだなって気づかされているんです。
お子さんがいる方、いない方それぞれの人生があって、大切なのは、それを自分がどう捉えるのかだと思います。私自身が、20代、30代で仕事を頑張ってキャリアを積むことができたのは、子どもがいたら難しかったかもしれない部分もあるので、そこは私自身の選択だったのかなと今は思います。
―自己決定できることもあれば、どうにもならないこともある。様々な紆余曲折を経られた今、これまでの歩みを納得して受け止めることができているのですね。悩み、迷いながらも一歩一歩ご自身を肯定されてきた道筋を、たくさん聞かせてくださり本当にありがとうございました。
これが最後のご質問になります。まきさんの、今後の人生の目標についてお聞かせください。
現在私は、看護師としての仕事は一旦お休みし、聖マリアンナ医科大学の研究室に研究員として所属しています。ここでは、医療現場に高度な人工知能を搭載したロボットを導入することで、患者さんやそこで働くスタッフへの影響について、実証実験を行っています。
例えば小児科の病棟でお子さんの相手をする医療職って、保護者に替わって辛い治療に前向きになるよう働きかけたり、治療が続けられるようサポートしてあげたりととても大変で、それだけにストレスがたまりやすいんですね。
そんな医療現場にロボットを導入したところ、子どもたちが可愛いと喜んでくれるだけでなく、実は看護師さん側もすごく癒されたと言ってくれて。双方にいい影響が出るのではないかとなったんです。
それに、ロボットを経由すれば、患者さんの家族と医療従事者がもっと気軽に会話できるきっかけも作り出せますよね。そうすることで病棟の雰囲気が明るくなり、患者さんやそのご家族、医療従事者みんなが元気になるなら、それは私にとってすごく嬉しいことだと思って、研究を続けています。
プライベートについては、今までと大きく変わらず過ごしていくのではないかな。こんな私でもいいよとともに生きてくれる人がいたら、一緒に過ごしてみたいなという願望はあります。
子どものことはその方との相談になってしまいますが、この先の人生も長いので、楽しいこと、苦しいことも話し合いながら、一緒に生きてくれる人がいたら嬉しいですね。

取材・文 / 内田朋子、写真 / 本人提供、編集 / 青木 佑、協力 / 高山美穂
\あなたのSTORYを募集!/
UMU編集部では、不妊、産む、産まないにまつわるSTORYをシェアしてくれる方を募集しています。「お名前」と「ご自身のSTORYアウトライン」を添えてメールにてご連絡ください。編集部が個別取材させていただき、あなたのSTORYを紹介させていただくかもしれません!
メールを送る

